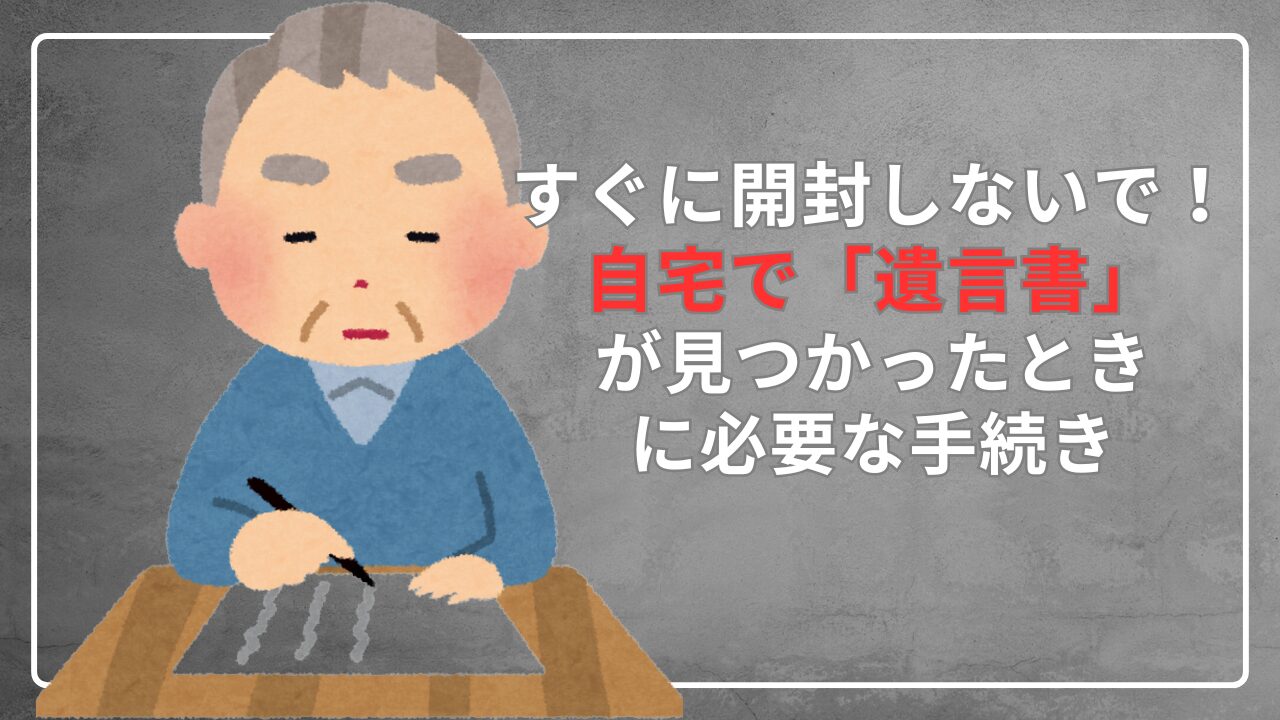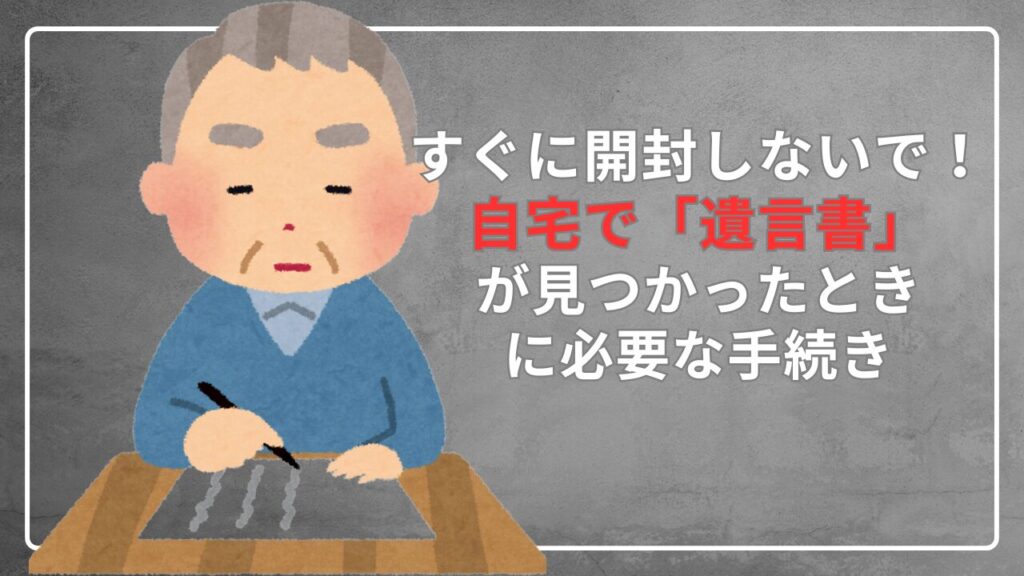
まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、相続に関する問い合わせやご質問も増えています。その中で、「身内が亡くなり、自宅で遺言書が発見されました」というと相談もあります。そこで今回は、「自宅で見つかった遺言書の対応」について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
自筆証書遺言には「検認」が必要
身内が亡くなった後、自宅の整理をしていると「遺言書」が見つかることがあります。突然の発見に驚き、すぐに中身を確認したくなるかもしれませんが、そのまま開封するのはNG です。遺言書の種類によっては、法律に則った手続きをしないと無効になったり、罰則を受けたりする可能性があります。この記事では、自宅で遺言書を発見した際に取るべき手続きを解説します。
遺言書を見つけたら絶対に開封しないで!
もし封がされた遺言書(封筒入りのもの)を見つけた場合、すぐに開けて中身を確認してはいけません。遺言書の種類によっては、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要だからです。
開封するとどうなる?
封がされた「自筆証書遺言」を本人以外が勝手に開封すると、民法第1005条により5万円以下の過料(罰則) が科されることがあります。
まずは 遺言書の種類を確認する
| 遺言の種類 | 検認の必要性 | 特徴 |
| 自筆証書遺言 | 必要 | 本人が手書きで作成し、署名・押印したもの。封筒入りの場合は開封せずに裁判所へ。 |
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証役場で作成され、公証人と証人2人が関与。すぐに効力を発揮できる。 |
公正証書遺言なら、そのまま手続きへ
公正証書遺言は家庭裁判所の「検認」が不要で、そのまま相続手続きに進めます。
自筆証書遺言なら、家庭裁判所へ
封を開けずに、家庭裁判所で「検認」の手続きを行いましょう。
検認手続きの流れ
「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認し、偽造・改ざんを防ぐための手続きです。検認を受けないと、遺言書を使った相続手続きができません。
検認手続きの手順
1️⃣ 遺言書の保管者または発見者が家庭裁判所に検認を申し立てる
- 被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て
- 必要書類:
- 遺言書
- 申立書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
2️⃣ 家庭裁判所が相続人に通知を送る
- 申立後、家庭裁判所が相続人全員に「検認期日」の通知を送付
3️⃣ 家庭裁判所で遺言書を開封し、内容を確認する
- 申立人が指定された日に出頭し、裁判官の立ち会いのもと遺言書を開封
- 内容が記録され、検認済証明書が発行される
4️⃣ 検認済みの遺言書を使って相続手続きを進める
- 遺言書に従って遺産分割や登記、銀行手続きを行う
重要ポイント
検認手続きは遺言の有効性を判断するものではないため、内容に問題がある場合は後に無効とされる可能性もあります。
遺言書が無効になってしまうケース
せっかく遺言書があっても、次のような理由で無効になることがあります。
🔸 法的要件を満たしていない(例:自筆証書遺言なのに署名・押印がない)
🔸 遺言能力がないと判断される(例:認知症が進行した後に作成された)
🔸 不正な方法で作成された(例:第三者が内容を偽造した)
不安な場合は専門家に相談し、遺言の有効性を確認しましょう。
遺言書を見つけたら、まず冷静に!
✅ 封がされている遺言書は開封せず、家庭裁判所へ
✅ まずは遺言書の種類を確認し、必要な手続きを取る
✅ 自筆証書遺言は「検認」が必要
✅ 公正証書遺言なら、そのまま相続手続きへ
✅ 遺言書の内容に問題がないか、専門家に相談するのも◎
遺言書は故人の大切な意思を示すものです。誤った対応をしないよう、慎重に手続きを進めましょう。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
今回は、自宅で遺言書が見つかった場合に、必要な手続きについて解説しました。
人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。
墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。