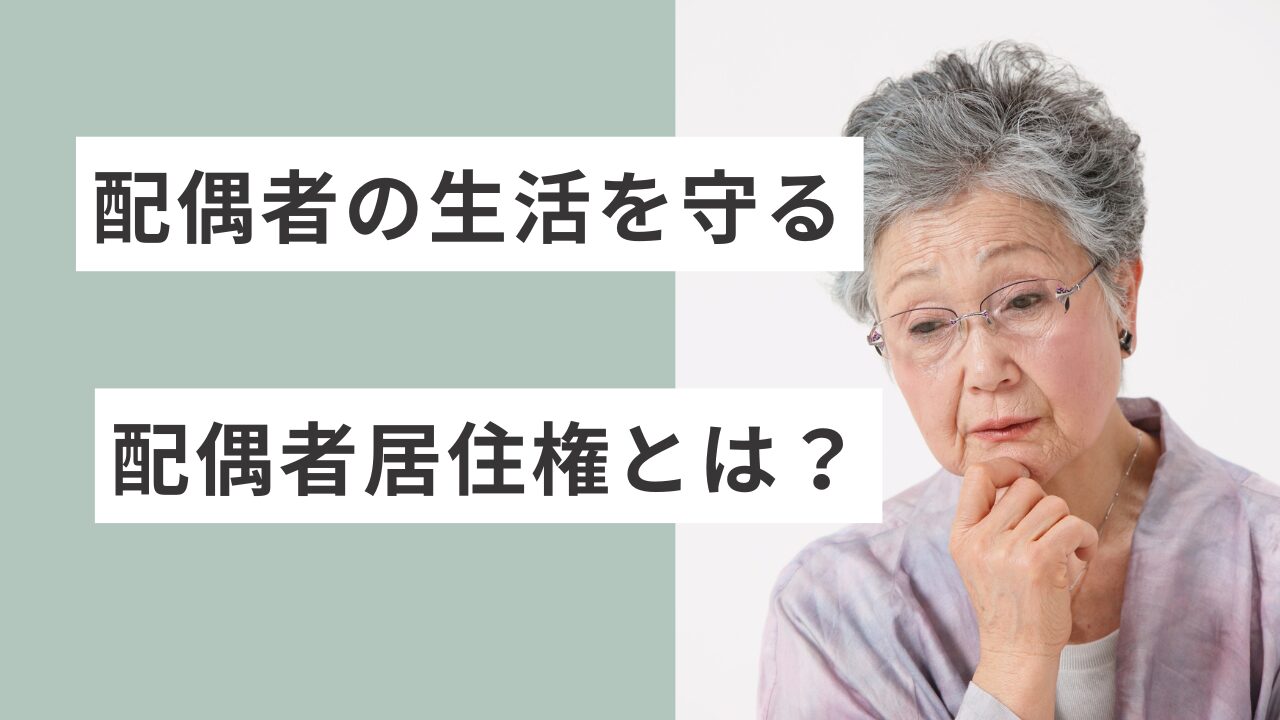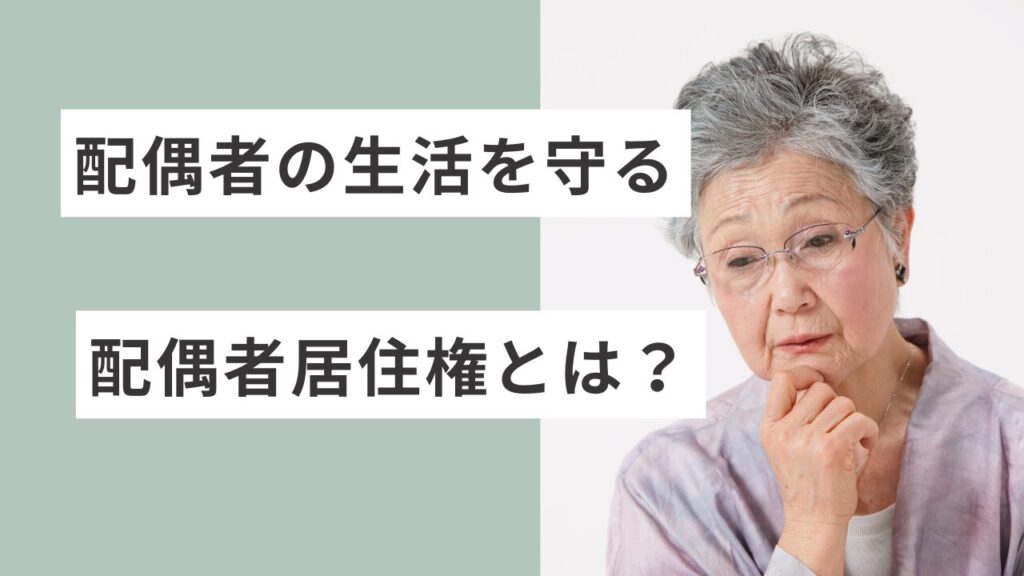
まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、相続に関する問い合わせやご質問も増えています。相続の相談として多いのが「自分が亡くなった後の、配偶者の今後の生活が心配」というものです。そこで今回は、「配偶者居住権」について解説します。老後や死後のことについては、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。
配偶者が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」
配偶者居住権は、2020年4月1日に施行された改正民法により新たに導入された制度で、配偶者が相続時に自宅に住み続ける権利を確保するためのものです。この制度により、配偶者は自宅の所有権を取得しなくても、一定の期間または終身にわたり住み続けることができます。
配偶者居住権のメリット
メリット1 住まいの確保
自宅の所有権を取得しなくても、亡くなった配偶者が住んでいた家に住み続けられる。
メリット2 相続財産の有効活用
自宅の所有権を他の相続人に分けながらも、住む権利を確保できる。
メリット3 相続税の軽減
所有権を取得するよりも相続税の負担が少なくなる可能性がある。
配偶者居住権の取得方法
配偶者居住権を取得する方法は、以下の3つです。
- 遺産分割協議:相続人同士で話し合い、配偶者居住権を認める。
- 遺言:被相続人が生前に遺言書で配偶者居住権を指定する。
- 家庭裁判所の審判:相続人間での合意が難しい場合、裁判所の判断で配偶者居住権が認められることがある。
配偶者居住権の制限と注意点
配偶者居住権については、以下のような制限があり、注意が必要です。
売却や賃貸は不可:配偶者居住権は譲渡できず、第三者に売ることも貸すこともできません。
建物の管理義務:配偶者は住んでいる家の維持管理を行う義務があります。
期間の制限:配偶者居住権は「終身」または「一定期間」など条件が付く場合があります。
配偶者居住権は、遺産分割において配偶者の住まいを確保しつつ、財産を有効活用できる制度です。ただし、設定方法や相続税の影響なども考慮する必要があります。制度の活用を検討する際は、専門家にご相談することをおすすめします。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
今回は、残された配偶者の生活を守る制度「配偶者居住権」について解説しました。
ただこのように、現実問題として終活に取り組んでいる方は、実は稀です。多くの方は、「まだ先で大丈夫」と考えているようです。ただ、「いつかやればいい」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあるのです。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。
墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。