
家族の絆を大切にし、将来にわたって資産を守り育てていくためには、相続や贈与について計画的に考えることが大切です。しかし、これらの分野は法律や税金にもかかわる問題ですし、個人の状況によって対策も変わります。適切な知識と情報を得ながら、最適な判断をしていくことが必要です。この記事では、2024年から適用される税制改正にも触れながら、「相続」「贈与」についてお伝えしていきます。
【目次】
相続と贈与はどう違う?
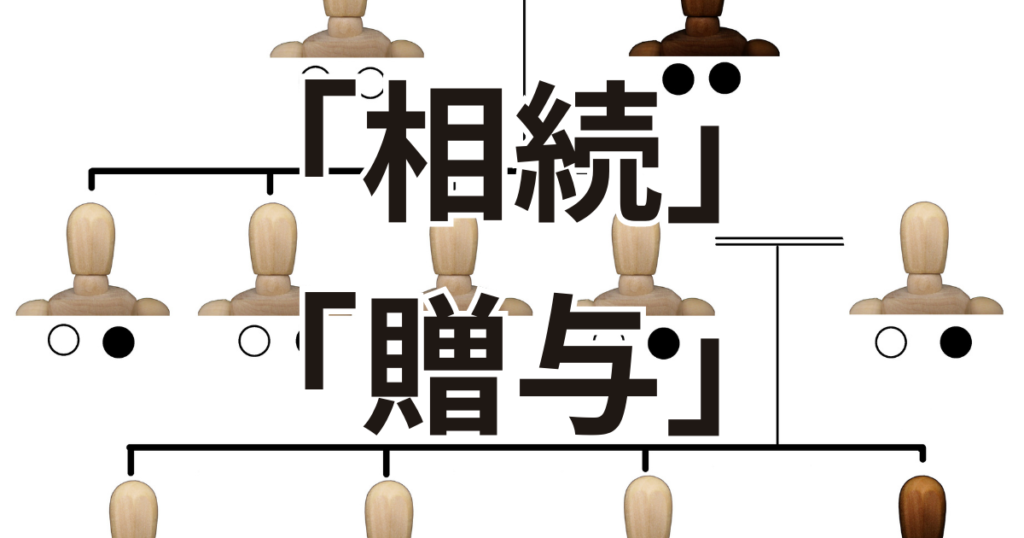
まずは相続と贈与の違いについてお伝えします。
相続と贈与は、どちらも財産を誰かに与えることです。ただ、どのタイミングで財産を与えるのかによって違いが出ます。
「贈与」は財産の所有者が生きているうちに財産を与えるもの。
そして「相続」は。原則として所有者が亡くなった後に財産の所有権の移転が発生するものです。
ご自身の財産を、誰に、どのタイミングで渡すかを生きているうちに決め、実行できるのが贈与。亡くなった後に、遺言書や法律の定めに基づいて財産を分配するのが相続と言えるでしょう。
相続or贈与 どちらが得?
相続と贈与はどちらも「相続税」「贈与税」という税金が発生します。これらは、財産を受け取った側に支払い義務が発生します。
納税の義務が発生しない「基礎控除」があり、控除額の範囲内であれば、税金が発生しません。
相続税の基礎控除額の基準は
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
となります。
例えば、法定相続人が妻・子ふたりの合計3人であれば、
3000万円+(600万円×3人)=4800万円
このケースでは、遺産が4800万円以下であれば相続税は発生しません。
あなたの遺産額や相続人の人数を当てはめて、この範囲内に収まるか、計算してみましょう。
遺産額が基礎控除額内で、配偶者や子どもなどの法定相続人に財産を渡したい場合は、相続がおすすめです。
また、贈与がおすすめのケースとしては
祖父母などからの教育資金
父母などからの結婚・子育て資金
祖父母・父母などからの住宅取得金
などです。
これらは、要件を満たせば贈与税の非課税枠になります。
特定の相手に対する資金の援助や、将来価格の変動が見込まれる不動産を所有している場合は、生前贈与を検討するのも良いでしょう。
税改正のポイントは3つ

2024年1月1日以降にうけた贈与から、あらたな税制が適用されます。
改正のポイントは以下の3つ
- 相続時精算課税に係る基礎控除の創設
- 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
- 暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
これをきっかけに、生前贈与について考えてみるのも良いでしょう。
ただ、税申告や適用の範囲についてはさまざまな要件が求められます。
「相続と贈与、どちらが得か?」
「実際に生前贈与するとしたら、どのような手続きが必要か?」
といったことは、専門家に相談することをおすすめします。
法的な手続きを円滑に進めるためにも、専門家の助言を受けることが重要です。
家族の状況に合わせた道筋を立てよう
相続や贈与には、家族構成や資産状況など、個々の状況に合わせたアプローチが必要です。あなたのニーズや目標に基づいて、最適なプランを立てていきましょう。家族の利益を守りながら、将来の安定を確保するためにも、専門家の意見を聞くことをおすすめします。
元気なうちに話し合って、トラブルを回避
相続に関しては、遺産分割や遺産トラブルのリスクも存在します。また、亡くなった後のご遺体の安置先や葬儀、遺産整理といった煩雑な手続きが、家族の関係にしこりを残してしまうケースもあります。家族や親しい人々との関係を損なうことなく、円満な相続を実現するためにも、専門家のサポートは不可欠です。死後事務委任契約を結んでおくことで、トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
避けては通れない“お墓”の問題
相続や贈与について家族で話し合うチャンスがあれば、“お墓”についても考える機会にしてください。近年では、「お墓を継ぐ後継者がいない」「子どもたちは県外で暮らしていて、お墓の管理ができない」といった理由から、“墓じまい”に取り組む方も増えています。“お金”や“お墓”については、差し迫ってからでは冷静な判断ができないこともあります。ぜひ元気なうちに取り組んでおきましょう。
まとめ
高齢化社会にともない「相続」「贈与」という話題も注目されています。当協会では、複雑な法律や税金の問題、個人の状況に合わせたプランの提案など終活に関するサポートを行っています。相続や遺言作成、死後事務委任契約、墓じまい、海洋散骨など、気になっていることがあればぜひお問い合わせください。
無料相談はこちら↓




