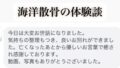“対話の場”は、海でもいい?という考え方
「仏壇とは、先祖との対話の場である」
お願い事をしたり、
悩み事を打ち明けたり、
人生の節目でそっと報告をしたり。
かつて、仏壇の前は、家族の誰かが手を合わせる“心の拠り所”でした。
私たちは、目には見えないご先祖様の存在を、
仏壇という“かたち”を通して感じ、
そこに語りかけ、力を借りてきました。
「仏壇を処分したら、子孫が困る」と言う人がいます
「そんな大切な仏壇を処分するなんて」
「将来、子や孫が困るのではないか」
「供養を絶やすなんて、罰が当たる」
こうした言葉は、仏壇処分や墓じまいを考えた人の多くが一度は耳にすることです。
でも、果たして本当にそうでしょうか?
子孫が困るのは、
仏壇が“あるか・ないか”ではなく、
“どう祈ればいいのか分からない”ことではないでしょうか。
仏壇という“対話の場”がなくても、
その心が受け継がれていれば、
祈りは形を変えて続いていくのではないでしょうか。
仏壇がなくなったら、祈りは消えるのか?
かつては、
家族が集まる部屋に仏壇がありました。
毎朝手を合わせる姿が子どもたちにとって自然な風景であり、
そこで“祈る”という行為が生活の中に根づいていました。
けれど、今は暮らし方も家族の形も変わりました。
マンション暮らしで仏壇を置く場所がない
お寺の行事に馴染みがなくなった
子どもたちが遠方で生活し、実家の仏壇に手を合わせる機会もない
海が仏壇になったという人たち
海洋散骨という供養のかたちを選ぶ人が、年々増えています。
理由はさまざまですが、
墓じまいや仏壇じまいとあわせて、
“新しい祈りの場”を求めての選択でもあります。
ある方は、こう語りました。
「仏壇もお墓もなくしたけど、私は迷ったとき、海に行くんです。
波の音を聞きながら、父に話しかけています。
昔は仏壇の前でしていたことと、なんにも変わらないですよ」
その方にとって、
“対話の場”は仏壇から海へと、自然に移っていたのです。
海という場所のちから
海は、癒しの場所です。
仏壇のように、家の中にある対話の場とは違い、
海は世界中どこにいてもつながっている場所です。
- 遠く離れていても、海を見ればそこに話しかけられる
- 子や孫が別々の土地で暮らしていても、同じ空と海の下で祈れる
- 自然とともに生きる祈りのかたちを、次の世代に残せる
海は、物ではないけれど、
確かな“祈りの場”になれるのです。
仏壇を処分しても、祈りは消えない
仏壇を手放すことに罪悪感を持つ人は少なくありません。
けれど、それは「文化を手放す」ことではなく、
「形に頼らず、心を受け継ぐ」という行為でもあります。
たとえ仏壇がなくても、
手を合わせたい気持ちがあれば、
ご先祖様との対話は続いていきます。
仏壇が“場所”として果たしていた役割を、
海が引き継ぐという考え方。
それは決して軽いものではありません。
むしろ、今の時代にふさわしい、
“供養の再構築”なのかもしれません。
仏壇とお墓を手放し、「海」という新しい拠り所へ
私たち「一般社団法人まるっと終活大分支援協会」では、
仏壇じまい・墓じまい・海洋散骨という選択肢を、
一つの流れとしてご提案しています。
- 仏壇という形ある祈りの場を手放す
- お墓という物理的な管理から解放される
- そして、祈りの場を“海”という誰にも開かれた場所に移す
それは、祈りを終わらせるのではなく、
もっと自由に、もっと自然に、
“生きている人の心”に寄り添う祈り方です。
最後に
仏壇とは、先祖との対話の場です。
だからこそ、その役割を誰かが引き継げないとき、
その対話の場を「次の形」に移すことは、
とても優しい選択なのではないでしょうか。
仏壇がなくても、
祈りは消えません。
むしろ、海の前で手を合わせる人々の姿を見ていると、
祈りの力は、形にとらわれないほうが深くなるのかもしれない――
そんなふうに思うのです。
仏壇じまいや海洋散骨についてのご相談は、こちらへ
どこにいても手を合わせられる、
新しい祈りのかたちを、一緒に考えてみませんか?