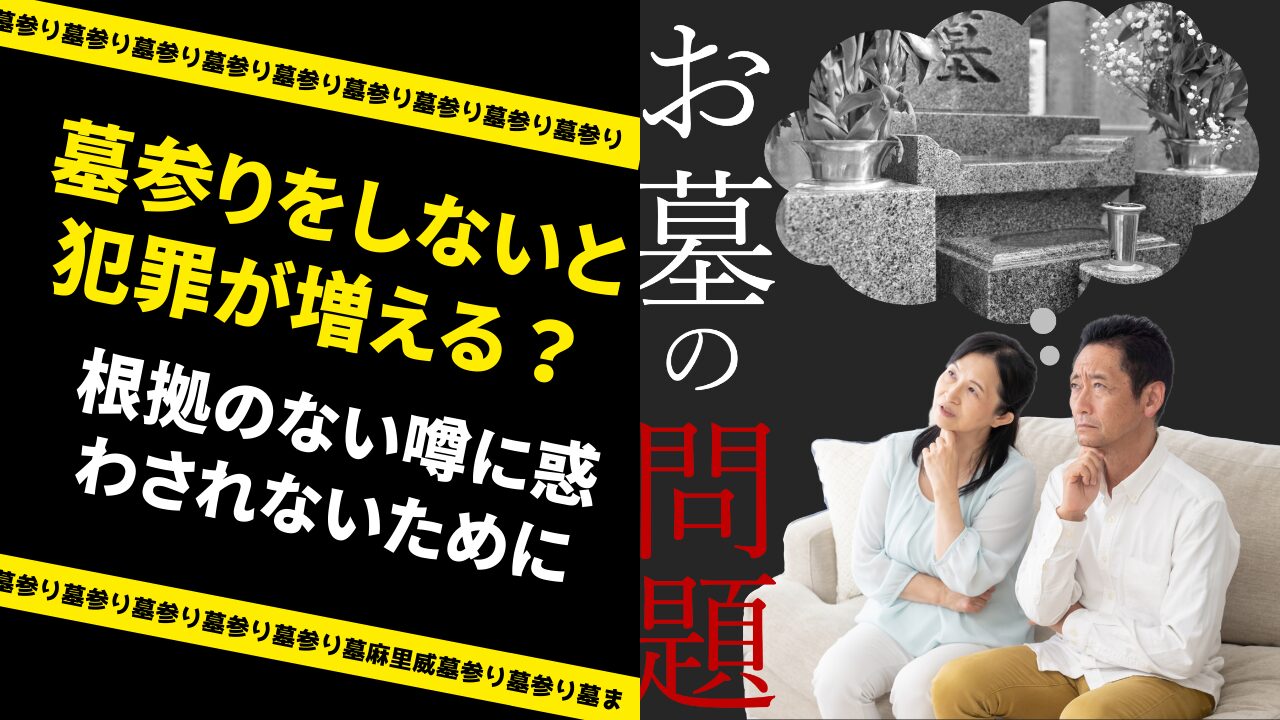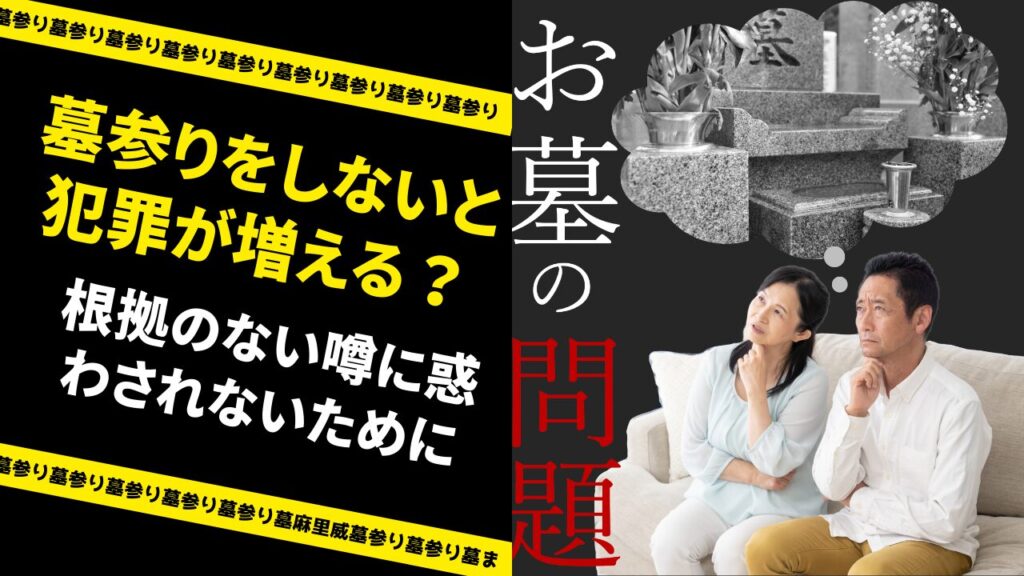
「墓参りをしないと犯罪率が高くなる」
こんな言葉を耳にしたことはありませんか?一見、もっともらしく聞こえますが、実はこの主張には科学的な根拠は一切ありません。むしろ、その背景には「ビジネス上の思惑」や「古い価値観」、「差別」が潜んでいる場合が多いのです。今回は「大分で増えている墓じまい」の現場から、この根拠のない噂を批判的に考えてみます。
「お墓文化」の実情
まず知っておきたいのは、お墓を持つ・持たないは、生まれ育った家の経済状況や立地環境に大きく左右されてきたという事実です。
お金持ちの家では、立派なお墓を建て、一族が近隣に暮らすことで自然に「墓参り」の風習が根付きやすい環境がありました。
一方で、次男や三男の家系は新しくお墓を建てなければならず、経済的な負担も大きい。地方から都市部へ移住した家庭では、近くにお墓がなく、そもそも「墓参り」を行う前提条件すら存在しません。本家の墓には入れず、自ら新しいお墓を建てる必要があります。また、移住してきた家庭には地域に先祖代々のお墓がなく、新しく作るか、作らずに過ごすしかありません。
つまり、子どもが生まれながらに「お墓の有無」が家庭環境によって決まるのです。
では、新しいお墓を建てなかった家に生まれた子どもたちが犯罪率が高いのか?――そんな統計は存在しません。よって「墓参りをしないと犯罪が増える」という理屈は破綻しています。「お墓があるかどうか」は個人の道徳心や犯罪率とは無関係であり、むしろ社会構造や経済格差によって決まる側面が強いのです。生まれながらにお墓のない子供はどうすればいいのでしょうか?生まれながらにお墓がないからといって「犯罪者予備軍」として見られてもよいのでしょうか?お墓がない家庭で育った子供は犯罪者になる確率が高いのでしょうか?私はこの視点に疑問を感じます。
日本の供養文化の歴史的事実
昭和30年代に火葬が一般化し、墓地埋葬法が整備されるまで、庶民は必ずしも「遺骨を残す」習慣を持っていたわけではありません。
昔は土葬で自然に還し、手を合わせる対象は仏壇や位牌という「形代(かたしろ)」でした。
遺骨を代々守る文化は比較的新しいものにすぎません。
なぜ「墓参りをしないと犯罪が増える」と言うのか?
このような噂を広めるのは誰か——それは、多くの場合 お墓や供養に関わる業界 です。
- 石材店:墓石需要を守るために「お墓を持たないのは不孝」と語る。
- お寺:檀家離れを防ぐために「墓参りを怠ると罰が当たる」と説く。
- 仏壇店:売上減少を背景に「仏壇がないと先祖を粗末に扱う」と主張する。
もちろん、すべてがそうだとは言いません。しかし、こうした言説が不安をあおり、消費者を伝統的な供養スタイルに縛りつける言葉として使われてきたのかも知れません。
現代の供養は「多様性」がキーワード
大分でも、少子高齢化や核家族化によって「墓じまい」を選ぶ家庭が増えています。
かつては「お墓があって当たり前」でしたが、今は「子どもに負担を残さない」「自然に還りたい」といった価値観を重視する時代となりました。
根拠のない噂に惑わされない
「墓参りをしないと犯罪率が高くなる」という噂は、科学的根拠のない言葉です。
むしろ、お墓や仏壇の有無に関わらず、人を思い、感謝を伝える心こそが供養の本質だと思います。お墓参りは大切な文化の一つではありますが、それを犯罪率と結びつけるのは論理の飛躍です。むしろ「お墓がない家」「お墓を持たない選択」をした人々を否定する根拠に使われることこそ問題です。
そして、墓じまい・仏壇処分・海洋散骨といった選択肢は、家族の負担を減らし、新しい時代に合った供養の形を示しています。
根拠のない噂や恐怖に縛られる必要はありません。大切なのは「自分と家族にとって納得できる供養のかたち」を選ぶことなのです。新しい供養の形を否定せず、尊重する社会こそが、人を孤立させず、犯罪を防ぐ土壌となるのではないでしょうか。