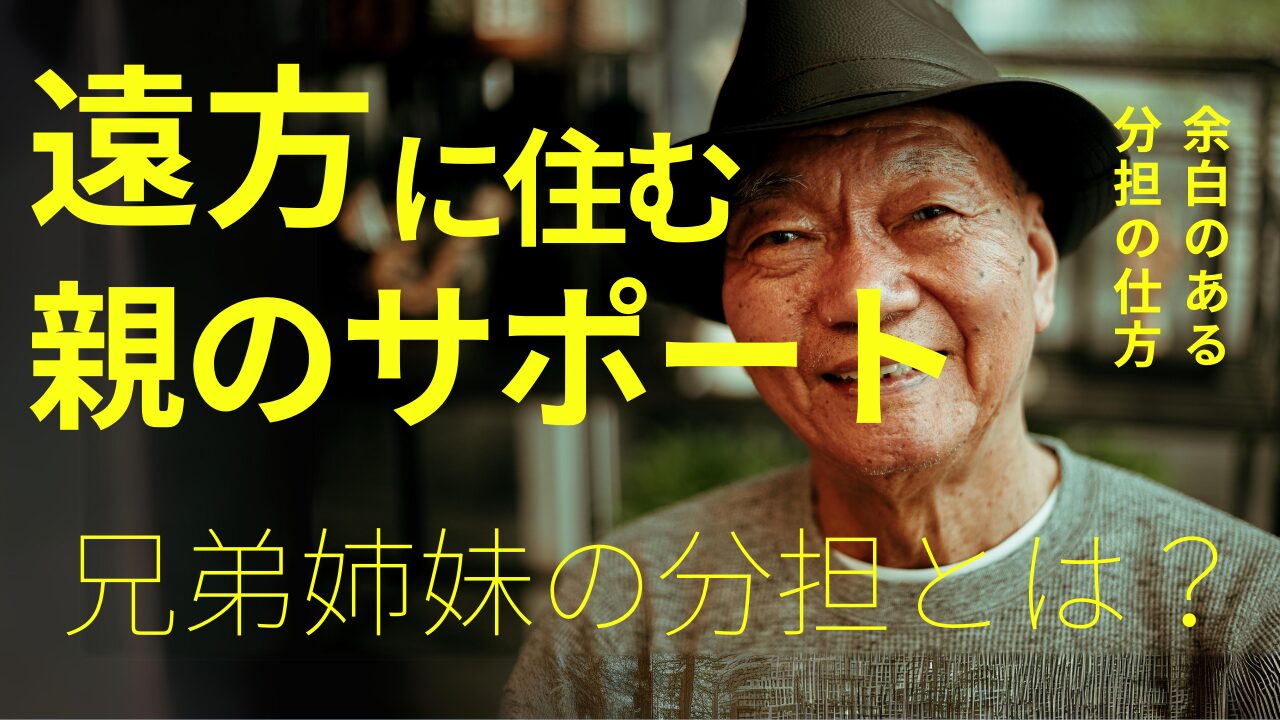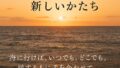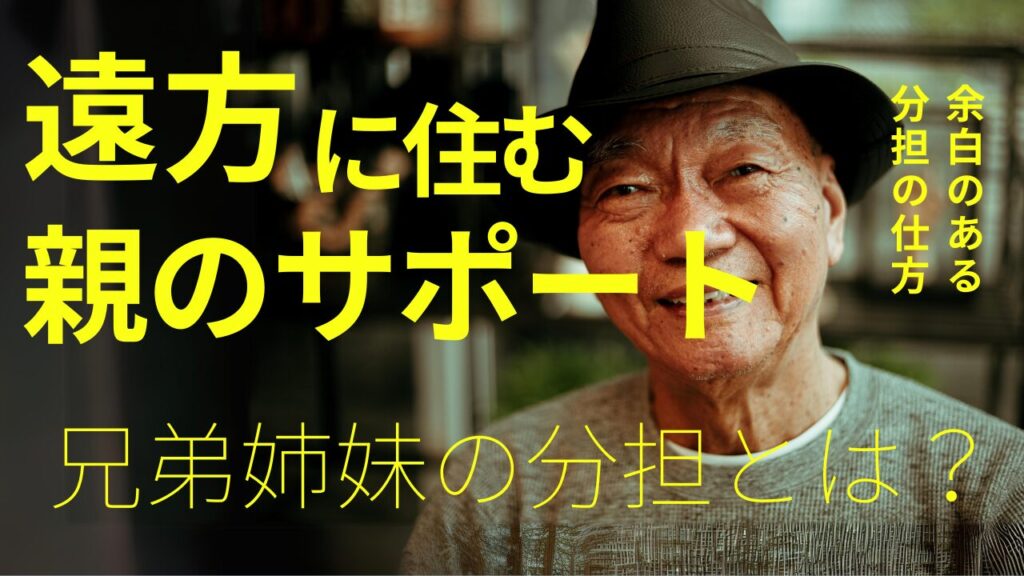
高齢の親のサポートが必要になってきたとき、避けて通れないのが兄弟姉妹との連携です。
「誰がどこまでやるのか」「何をどこまで話し合っておくべきか」——連携がうまくいけば、親も子どもたちも安心できますが、逆に意思疎通ができていないと、トラブルや不満が生まれがちです。
この記事では、遠方に暮らす高齢の親を支えるために兄弟姉妹で連携する際のポイントや、円滑に進めるための工夫について紹介します。
まずは情報共有からスタート
親の健康状態や生活状況に関する情報は、できるだけ兄弟姉妹で共有しておくことが重要です。
「誰かひとりが知っている状態」ではなく、全員が同じ情報を持っていることで、判断や相談がスムーズになります。
情報共有におすすめの方法
✅家族グループLINEやメールで定期報告
✅親との通話内容や体調の変化をメモして共有
✅帰省したときの写真や動画を送る
些細なことでも「見える化」することで、お互いの安心感につながります。
役割分担は“できる人が、できることを”
兄弟姉妹といっても、仕事・家庭環境・居住地などそれぞれ事情が異なります。
「長男だから」「近くに住んでいるから」といった理由だけで負担が偏ると、あとで不満が爆発することも。
大切なのは、“公平性”ではなく“納得できる分担”を見つけること。
以下に例を挙げてみます。
・近くに住む兄→病院の付き添いや日常のフォロー
・遠方の妹→定期的な電話や見守りサービスの手配
・ITに強い弟→家計や介護保険の手続き支援
「自分ができること」にそれぞれが責任を持つスタイルを見つけることで、長続きしやすくストレスも少なくなるでしょう。
金銭面の負担も話し合っておくことが重要
介護や見守りには、時間だけでなくお金もかかります。
親の年金や貯蓄でまかなえる場合もありますが、不足する場合は兄弟姉妹で補う必要があるかもしれません。
このとき、事前に費用の見通しと負担割合を相談しておくことが非常に大切です。曖昧なまま進めると、後で「誰がどれだけ出したのか」で揉める可能性も。
できれば、費用は記録を残しながら透明性を保ちましょう。
LINEのメッセージや共有フォルダなどに残すだけでも信頼感が違います。
意思決定のプロセスを共有する
親の介護や医療、施設入所の判断など、人生の大きな決断を迫られる場面では、家族間での意見が分かれることもあります。
そうしたときのために、「どう決めていくか」のルールを日頃から確認しておくと安心です。
✅親の意向を第一に尊重する
✅緊急時は誰が最終判断をするか
✅重要な話はオンラインで顔を合わせて話す
感情論ではなく「共通の基準」をもって話し合えるようにしておくことが大切です。
お互いに “感謝の言葉”を忘れずに
兄弟姉妹といっても、サポートは「当然の義務」ではありません。
誰かが頑張ってくれているときには、素直に「ありがとう」「助かるよ」と言葉にしましょう。
感謝を伝えることで、相手のモチベーションも保たれ、信頼関係が深まります。
「ありがとう」の言葉が、兄弟姉妹の絆も強くしてくれることでしょう。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
高齢の親のサポートは、長期戦になることも多く、1人だけで背負うには負担が大きすぎます。
兄弟姉妹がチームとして支え合えば、無理なく、親にとっても心強い環境を作ることができます。
「誰が何をするか」よりも、「どう支え合うか」が大切。
親の人生を穏やかに見守るために、兄弟姉妹でしっかり連携していきましょう。遠方で暮らす親の終活についてお悩みがあれば、当協会にお気軽にお問合せください。ご本人やご家族の気持ちに寄り添った終活の形をご提案します。
一人暮らしの親のご相談はこちらから↓