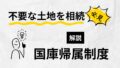孤独死という言葉は、今や珍しいものではなくなりました。大分でも高齢者の一人暮らしが増え、誰にも看取られずに亡くなる方が年々増加しています。そんな中で、遺骨をどうするか、供養をどうするかに悩む家族も少なくありません。
今回ご紹介するのは、孤独死した弟の遺骨を前に、兄が「墓じまい」と「海洋散骨」という選択をした実例です。
弟の孤独死、そして兄の決断
大分市に一人暮らしをしていた弟は、長い闘病の末、誰にも看取られずに息を引き取りました。身寄りは兄ただ一人。知らせを受けた兄は大阪から駆けつけ、弟の死を受け止めることになりました。
しかし、問題はその後です。両親の代から守られてきたお墓は大分にありますが、兄自身は遠方に住み、子どもたちも都会で生活しています。
「このまま弟をお墓に納めても、誰もお参りできない。いずれ墓じまいを子どもたちに背負わせるだけだ」
そう考えた兄は、弟の遺骨の行方を真剣に考え始めました。
墓じまいか、それとも別の道か
親戚からは「ご先祖のお墓に納めるのが一番だ」と言われました。しかし兄は、自分の子どもたちにまで墓守を背負わせることに疑問を抱きます。
お墓を持ち続けることは、維持費や管理の労力だけでなく、精神的な負担にもなります。墓じまいをするにも大きな費用と手間がかかり、さらに仏壇処分も避けては通れません。
「弟を自然に還す方法はないのだろうか」――。そこで兄が出会ったのが、海洋散骨という選択肢でした。
海洋散骨という答え
兄は思い出しました。弟が生前、よく「海が好きだ」と話していたことを。
「だったら弟を海に還そう。海はどこにいてもつながれるし、形はなくても心の中に残り続ける」
こうして兄は、大分で墓じまいと仏壇処分を進め、弟の遺骨を海洋散骨で自然に還すことを決めました。
当日は僧侶に依頼して簡単な読経をしていただき、その後、粉骨した遺骨を静かに海へと流しました。波に乗って散る花々を見ながら、「これで良かった」と深く頷きました。
孤独死と遺骨の行き先に悩む人たち
大分では、独居高齢者の増加とともに孤独死のリスクも高まっています。そして、残された家族は「遺骨の行き先」という現実的な課題に直面します。
- 遠方に住んでいてお墓を守れない
- 子どもが跡を継げない
- 仏壇を引き継ぐ人もいない
こうした状況の中で、「墓じまい」「仏壇処分」「海洋散骨」をセットで考える人が増えているのです。
供養の本質は「心にある」
今回の兄の決断が教えてくれるのは、供養の形に「正解」はないということです。
昭和30年代に火葬と墓地埋葬法が一般化するまでは、多くの人が土葬で自然に還り、供養は仏壇や位牌といった「形代(かたしろ)」を通して行われていました。遺骨にこだわる文化は比較的新しいものなのです。
海洋散骨は、古来の「自然に還す供養」の再生とも言えるでしょう。大切なのは「遺骨のありか」ではなく、「心にある故人への思い」なのです。
孤独死から考える新しい供養
孤独死は誰にでも起こり得る現実です。残された家族にとって、遺骨やお墓の問題は避けられません。
しかし、「墓じまい」や「仏壇処分」、そして「海洋散骨」という選択肢を知ることで、私たちは少しでも前向きに供養と向き合うことができます。
弟を失った兄が選んだ海洋散骨は、「負担を残さない」という優しさであり、「自然に還す」という願いでもありました。その姿は、これからの大分で広がっていく新しい供養の形を象徴しているのかもしれません。