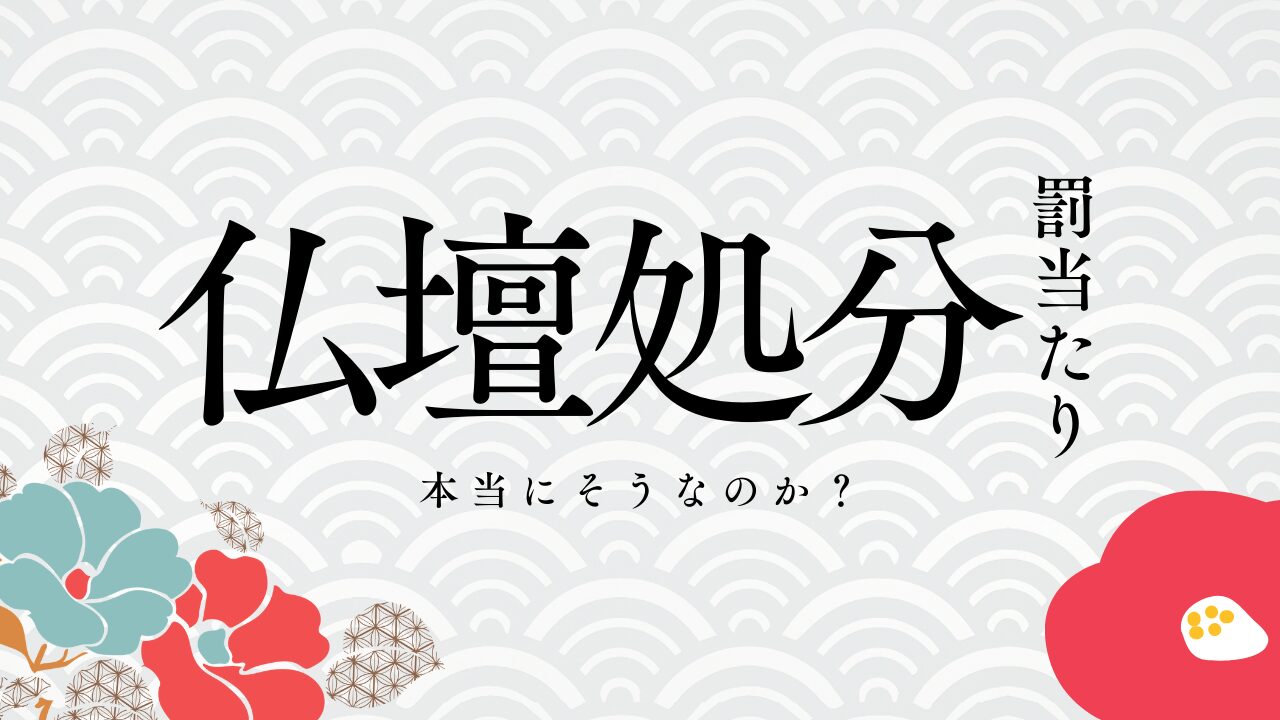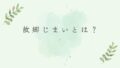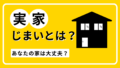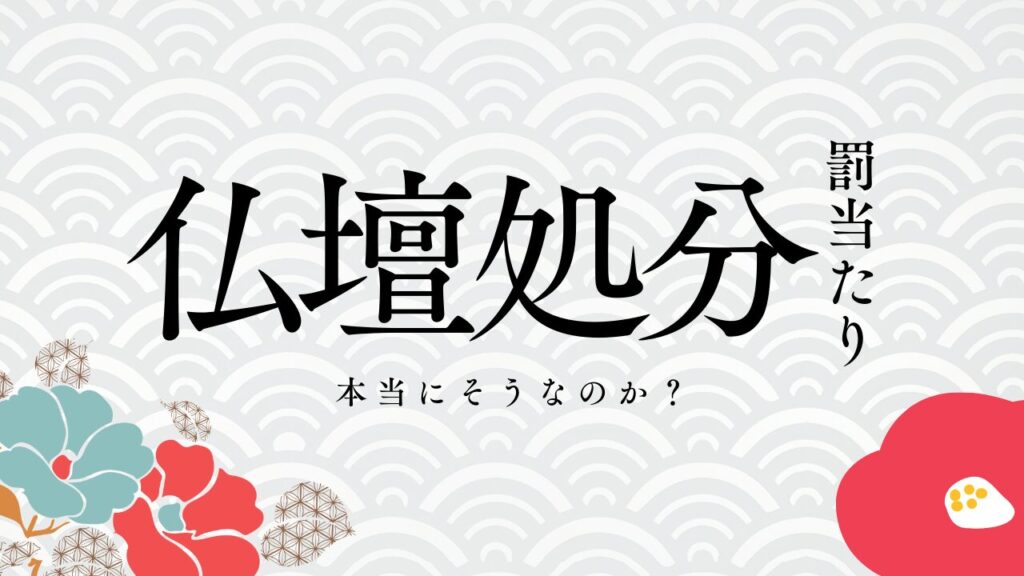
「仏壇を処分するなんて罰当たりではないか」
「お墓を守らなければ先祖に顔向けできない」
大分県でも、仏壇処分や墓じまいを検討するご家庭から、こうした声をよく耳にします。しかし実際には、核家族化や少子高齢化の進行によって「仏壇を引き継ぐ人がいない」「遠方に住んでいてお墓を守れない」と悩む方が増えています。
今回ご紹介するのは、そんな現実に直面したある女性の事例です。彼女は「仏壇を守るか」「海洋散骨を選ぶか」で心揺らぎながらも、最終的にはご主人の望みに寄り添い、自然に還すという決断をしました。
仏壇との別れを前にした葛藤
その女性は、夫を数年前に亡くしました。自宅には立派な仏壇があり、毎日そこで手を合わせるのが日課になっていました。しかし、彼女の子どもたちはすでに県外に暮らし、誰も仏壇を引き継げる状況にはありません。
ある日、仏壇処分のことを考え始めると同時に「では夫の遺骨はどうすればいいのだろう」と悩みは広がっていきました。墓を建立する選択肢もありましたが、夫は生前から「お墓はいらない、自然に還してほしい」と語っていたのです。
宗教者からの反対と「供養とは何か」の問いかけ
相談の過程で、菩提寺にあたる僧侶に話をしたところ「仏壇を処分すれば後悔する」「遺骨を残さないときっと寂しくなる」と強い反対を受けました。
女性は深く迷いました。しかし一方で、彼女の心の中には「夫の声」が残っていました。―「娘たちに負担をかけずに、海に還してほしい」という声です。
この体験は、「供養とは何か」という問いを私たちに投げかけます。供養の本質は、形式ではなく「心にある故人への思い」ではないでしょうか。
海洋散骨という新しい選択
最終的に女性は、仏壇処分を決断しました。そして夫の遺骨を海洋散骨で自然に還すことを選びました。
海洋散骨の当日、大分の海に家族が集まり、花を手向けながら「ありがとう」と声をかけました。波に揺れる花びらを見ながら、彼女は「夫が本当に望んでいたのは、この自由なかたちだったのだ」と心から感じたそうです。
その後、仏壇がなくなった家のリビングは少し広くなり、彼女は「夫は海にいる」と思いながら、時折大分の海を眺めに出かけるようになりました。海はどこまでも広がり、どこにいてもつながれる象徴になったのです。
大分で広がる「墓じまい」「仏壇処分」「海洋散骨」
大分県でも、墓じまいや仏壇処分を検討する家庭は年々増えています。背景には以下のような事情があります。
- 子ども世代が県外に出てしまい、跡継ぎがいない
- お墓や仏壇の維持に費用と労力がかかる
- 「自然に還りたい」という本人の希望
かつて日本では、埋葬と供養は別々でした。遺骨を残して手を合わせる文化が一般化したのは昭和30年代以降のことです。それ以前は土葬が主流で、遺骨を残さず自然に還すのが普通でした。
つまり、海洋散骨は新しい供養ではなく、「自然に還す」という古来のあり方に戻っただけなのです。
心に残る供養を選ぶ
仏壇処分も、墓じまいも、海洋散骨も、大切なのは「自分と家族が納得できる形」を選ぶことです。形式や慣習に縛られて後悔するよりも、心の底から「これでよかった」と思える選択が、何よりも尊い供養になるはずです。
大分で仏壇処分や墓じまい、海洋散骨を考えている方へ。どうか「誰かに言われたから」ではなく、「自分と家族が本当に望む形」を大切にしてください。海はいつでも、あなたの想いを受け止めてくれる場所です。