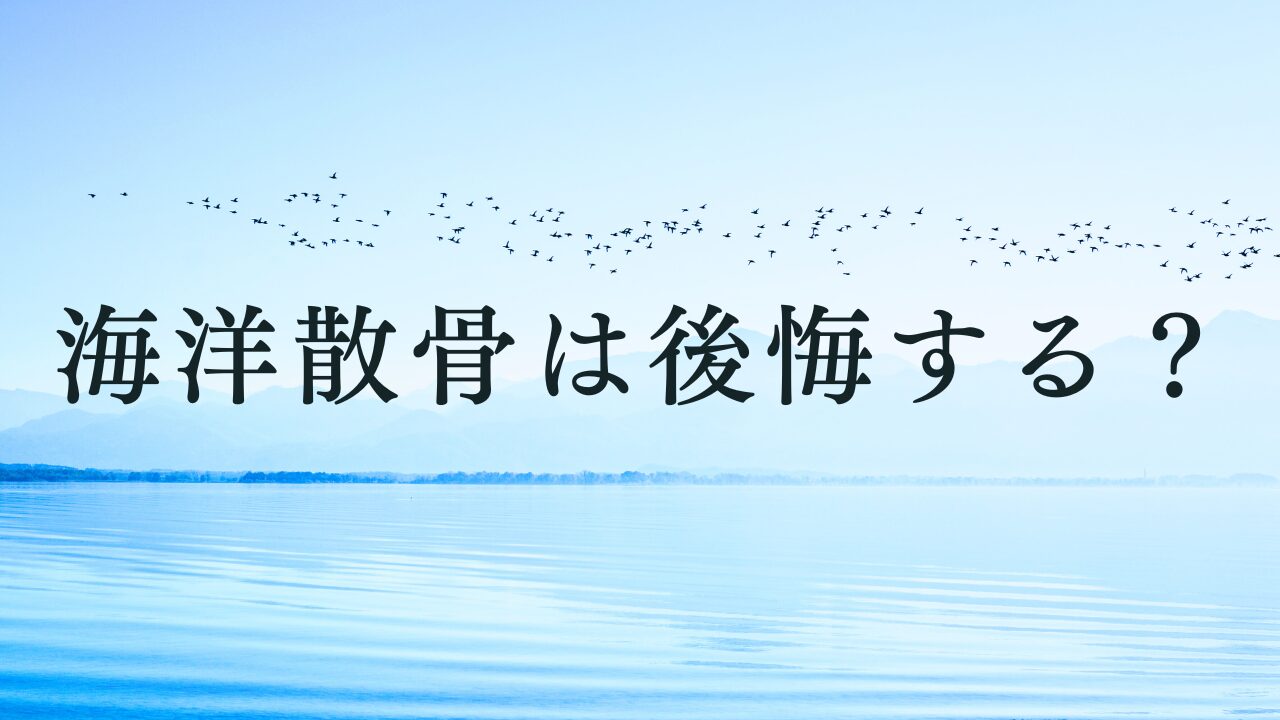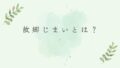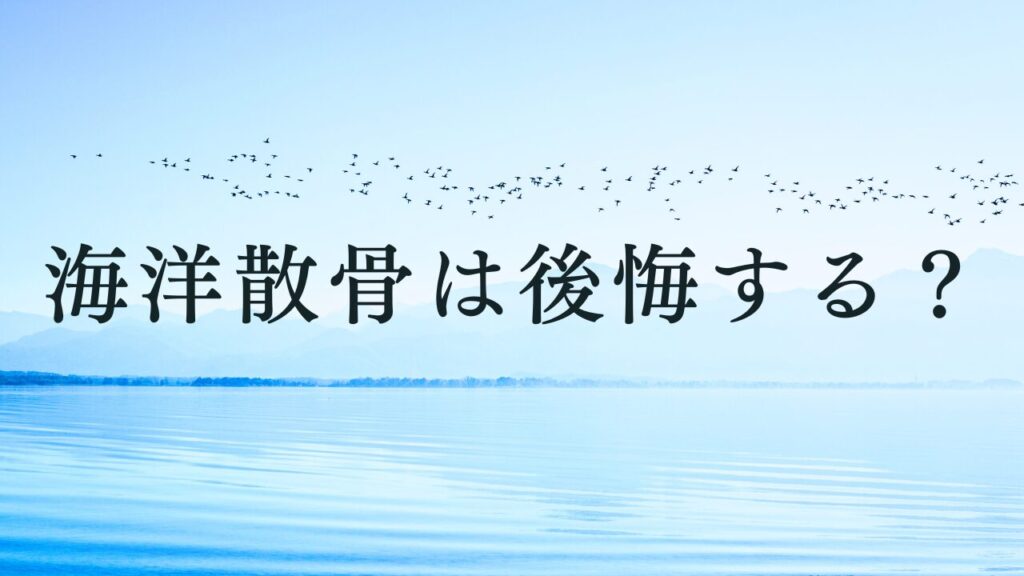
息子に迷惑をかけたくない——母の願い
数か月前、ある60代の男性からご相談をいただきました。
「母が高齢で病床にあり、もしものときには海洋散骨を希望している。自分たち家族はその意思を尊重したい」とのことでした。
お話を伺うと、母親はこう語っていたそうです。
「息子にお墓の負担を残したくない。海なら、どこからでも見えるし、手を合わせられる。海が私のお墓になれば、それで十分。」
その言葉は、子どもにとって大きな救いでもありました。
お寺からの反対と揺れる気持ち
ところが、ご家族が菩提寺に相談した際、住職からは厳しい言葉がありました。
「遺骨をなくしてしまったら必ず後悔する。せめて納骨堂に入れるべきだ」と。
親の願いを叶えるべきか、お寺のいうことに従うべきか——ご家族は揺れました。
しかし最終的に、母の「子どもに迷惑をかけたくない」という思いを尊重し、海洋散骨を選ばれました。
昔の供養は“遺骨を残さない”のが当たり前だった
現代では「遺骨を骨壺に入れて残す」ことが当然のように思われています。
しかし、歴史を振り返るとそれはごく最近の文化です。
昭和30年代に火葬が一般化し、墓地埋葬法が制定されてから「遺骨を残す」ことが普及しました。
それ以前は土葬や自然葬が主流で、遺骨を子供が引き継ぐという習慣はありませんでした。
人々は遺骨そのものではなく、位牌や仏壇という**形代(カタシロ)**に手を合わせてきました。
つまり供養の本質は「遺骨」ではなく「心」だったのです。
海洋散骨で後悔しないために
海洋散骨を選んだご家族からは、こんな声をいただきました。
「お墓を建てていないのに、母をちゃんと見送れるのか不安もあった。でも、海に手を合わせた瞬間、すっと心が軽くなった。これなら後悔しないと思えました。」
散骨は「遺骨が残らない」からこそ後悔すると言われることがあります。
しかし大切なのは、遺骨があるかどうかではなく、故人を思う気持ちをどう形にするかです。
多様性の時代に選ばれる供養
供養の方法はひとつではありません。
お墓に納めることも、納骨堂に預けることも、そして海に還すことも、すべては家族の思いによって選ばれるべきです。
文化や伝統は時代とともに変わります。
大切なのは、「残された人が後悔しないこと」「故人を思う心を持ち続けられること」。
海洋散骨を選ぶ人は年々増えています。
それは“お墓を持たない”という冷たい選択ではなく、次の世代を思いやる温かい選択なのです。
大分で海洋散骨
「海洋散骨は後悔するのでは?」という声は、いまも聞かれます。
しかし実際には、散骨を選んだ多くのご家族が「心が軽くなった」「自然と一体になれた」と語ります。
供養は形ではなく心。
海に還すことで、どこにいても海を見れば手を合わせられる。
その新しい供養のかたちを、ぜひ理解していただければと思います。