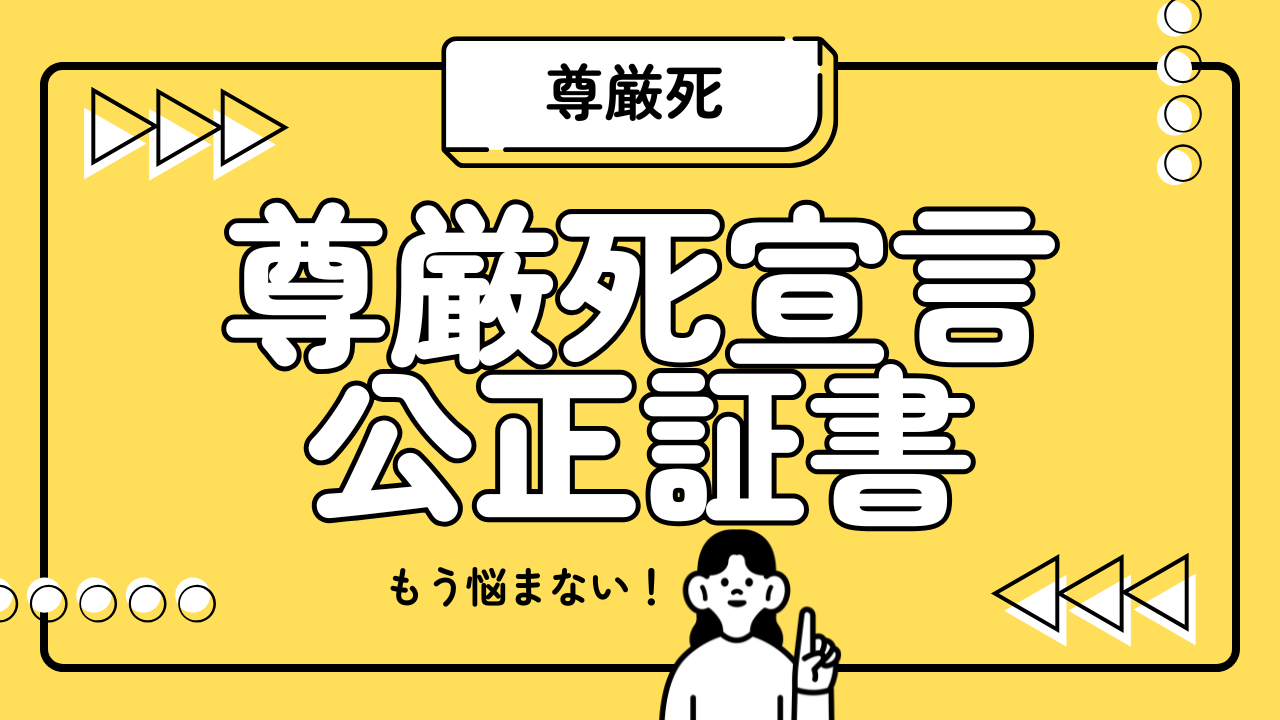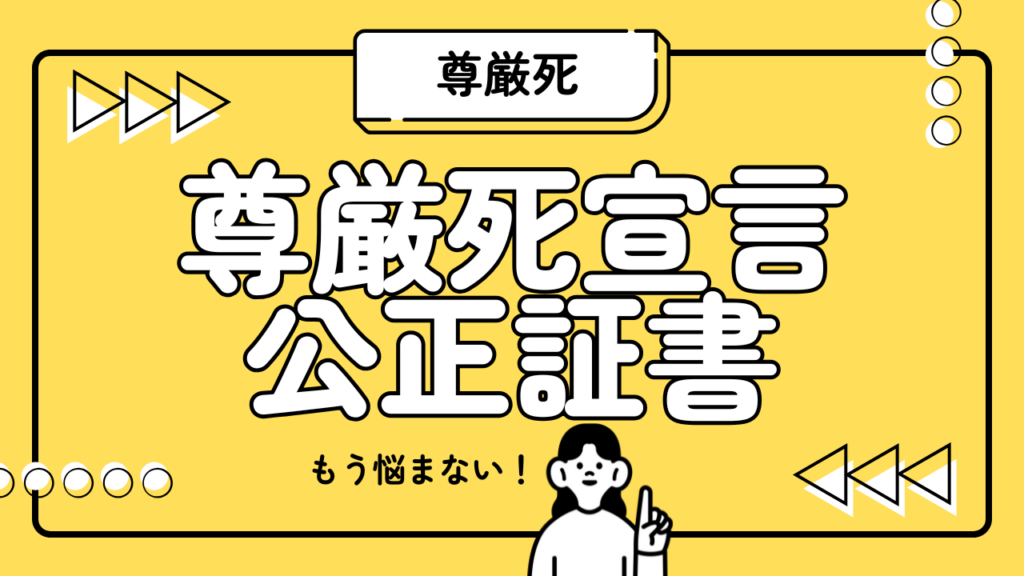
高齢化が進む大分県でも、「もしものとき、自分の意思をどう伝えるか」という悩みを持つ方が増えています。その中で注目されているのが「尊厳死宣言」です。延命治療をどこまで受けるかを事前に意思表示しておくもので、家族や医療現場での判断を助ける役割を果たします。そこで今回は、50代女性のお父様のエピソードをご紹介します。
「延命治療は望まない」その気持ちの伝え方
大分県で暮らす私の父は、数年前に体調を崩してから「もしものときに自分の意思をきちんと残しておきたい」と思ったようです。病院で延命治療について説明を受けたとき、「自分は延命だけのために管につながれて生きるのは望まない」と口にしていたのが印象的でした。
しかし、その思いを家族に伝えるだけでは不十分だということ知ったようです。いざという時、本人が意思表示できなければ、残された家族が「延命を続けるかどうか」という重い判断を迫られるからです。実際に、父の友人が「本院は延命治療を望んでいなかった」と言っても、きちんと書面に残していないために病院側が処置を続けざるを得ず、家族が悩み続けたというケースもあると聞きました。
家族の見解が分かれた、友人の意思
父の友人のAさんは、闘病生活を送っていました。Aさん本人は「延命は希望しない」と家族に伝えていたそうですが、書面や公的な意思表示はしていませんでした。その結果、いざ危篤状態になったとき、医師から「人工呼吸器をつけるかどうか」の判断を求められ、家族の間で大きく意見が分かれてしまいました。「生きていてほしい」という気持ちと「本人の意思を尊重したい」という思いがぶつかり合い、家族間に深い溝ができてしまったのです。
最期の治療についての希望は、公正証書に
父はその話を聞いて「自分は、家族に同じような思いはさせたくない」と感じたようです。そこで、尊厳死宣言公正証書を作成しました。これは公証役場で作ることができる正式な書面で、「どこまで延命治療を望むか」「自然な最期を迎えたい」という意思を明確に記すことができます。行政書士に相談しながら内容を整理し、公証人の前で署名・押印したことで、家族も安心しました。
作成してからは、父自身も「これで安心して余生を過ごせる」と穏やかになり、家族も「いざという時は父の意思を尊重すればいい」と心が軽くなりました。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
大分県でも尊厳死宣言をする人が少しずつ増えています。その背景には、家族が判断に迷い、トラブルになった経験を耳にする人が多いからでしょう。本人の意思を尊重するため、そして家族を悩ませないためにも、尊厳死宣言は大切な準備のひとつです。もし同じように悩んでいる場合は、行政書士や公証役場に相談してみることをおすすめします。
そのほか、終活についてお悩みがあれば、当協会にお気軽にお問合せください。ご本人やご家族の気持ちに寄り添った終活の形をご提案します。