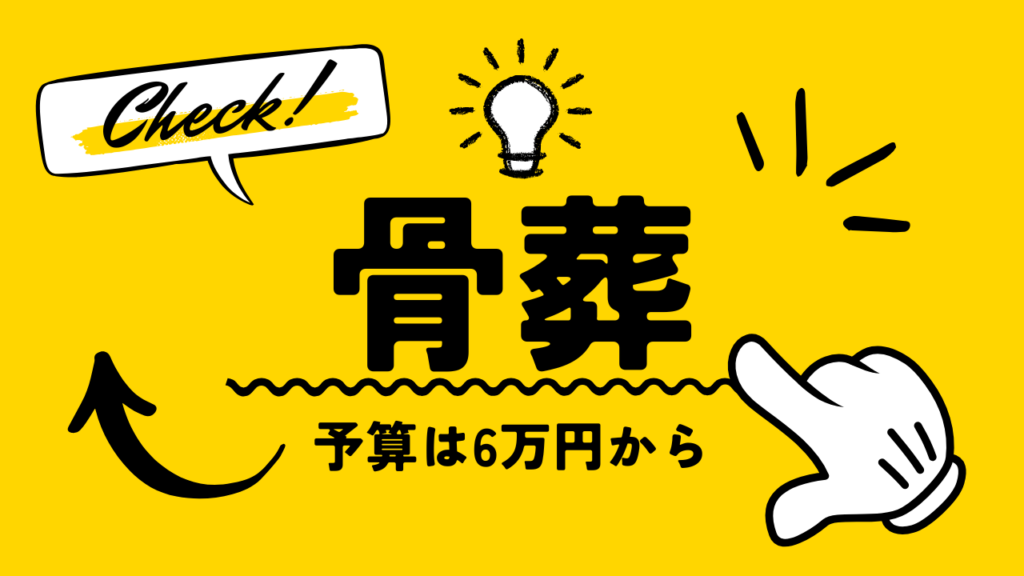
――火葬のあとに、たった数人で営む“ちいさなお別れ”の儀式
最近、「骨葬(こっそう)」という新しいかたちのお別れが、静かに広まりつつあります。
みなさんはご存知でしょうか?骨葬とは、故人を火葬したあとに、同居していた家族や、ごく近しい身内だけで行う、小さなお見送りの儀式です。
火葬のあとに、そっと営まれる「骨葬」という選択
葬儀と聞くと、多くの人が喪服を着て、セレモニーホールに集まり、厳かな読経が響く中で故人を偲ぶ……そんな光景を思い浮かべるかもしれません。
しかし私たちが執り行う「骨葬」は、それとはまったく異なります。
- 参列者は1人〜5人ほど。
- 会場は、葬祭ホールではなく、ごく小さなスペース。
- 服装は、普段着のままで。
- お花は、白菊や蓮ではなく、バラやカーネーションなど、カラフルでフェミニンなもの。
- 儀式の時間は、30分程度。
- 祭壇もコンパクト。飾る写真や思い出の品も自由。
どこか“儀式”というよりも、“心を込めたお別れ会”に近い雰囲気です。お茶を淹れたり、好きだった音楽を流したり、故人の好きだったお菓子を並べたり——そんな、あたたかで私的な時間です。
直葬(ちょくそう)+骨葬という新しい葬送スタイル
コロナ禍以降、「直葬」というスタイルも一般化しました。お通夜や葬儀をしないまま、火葬場へ直行する形式です。都心部では10人に2人、約20%近くが直葬(火葬式)というデータもあります。
けれど直葬は、「ちゃんとお別れできなかった」「何もしないのは心残り」という声も多くありました。
そこで今、火葬だけで終わらせず、あとから“骨葬”というかたちで、あらためて故人を偲ぶ。
こうした流れが注目されています。
特に——
- 子どもが遠方に住んでいるため親の交友関係が分からない
- 故人が高齢で交友関係が少なかった
- 親が亡くなったことを誰に知らせるか不明だった
- 形式ばった葬儀に違和感を感じる
- 少人数で、想いを深く伝えたい
こうした家庭において、骨葬は大切な“心の区切り”となるのです。
「祭壇の小ささ」ではなく「想いの深さ」が大切
骨葬の特徴の一つは、小さいことに引け目を感じる必要がないということです。それどころか、祭壇が小さいからこそ、お花の1本1本に、故人への想いがこもります。たとえば、ピンクのガーベラは「感謝」、カーネーションは「母への愛」、バラには「永遠の想い」。
骨葬の空間には、こうした思いや意味が宿っているのです。
火葬は必ず必要。だからこそ“骨葬”を
海洋散骨などで自然に還すスタイル——
現代では、お墓を持たない選択肢が増えました。
火葬は必ず必要です。
火葬の後、すぐに散骨してしまうのではなく、そのほんの少しの“間”に、お別れの時間を持つ。
それが骨葬です。
「きちんとお別れしたい」
「でも大げさにはしたくない」
「故人らしく、静かに、優しく送りたい」
そんな想いに寄り添うのが、骨葬という葬送のかたちなのです。
これからのお見送りのかたち
私たちは、これから「大きな儀式」よりも「心に残るひととき」を重視する時代に向かっているのかもしれません。
骨葬は、喪服も形式も必要ありません。
ただ、そこに“心”があることが大切です。
もしあなたが、ご自身の最期にどんな送り方を望むか、
あるいは、大切な人との別れにどんな時間を持ちたいか——
その答えの一つとして、「骨葬」という言葉を、そっと心に置いておいていただけたらと思います。



