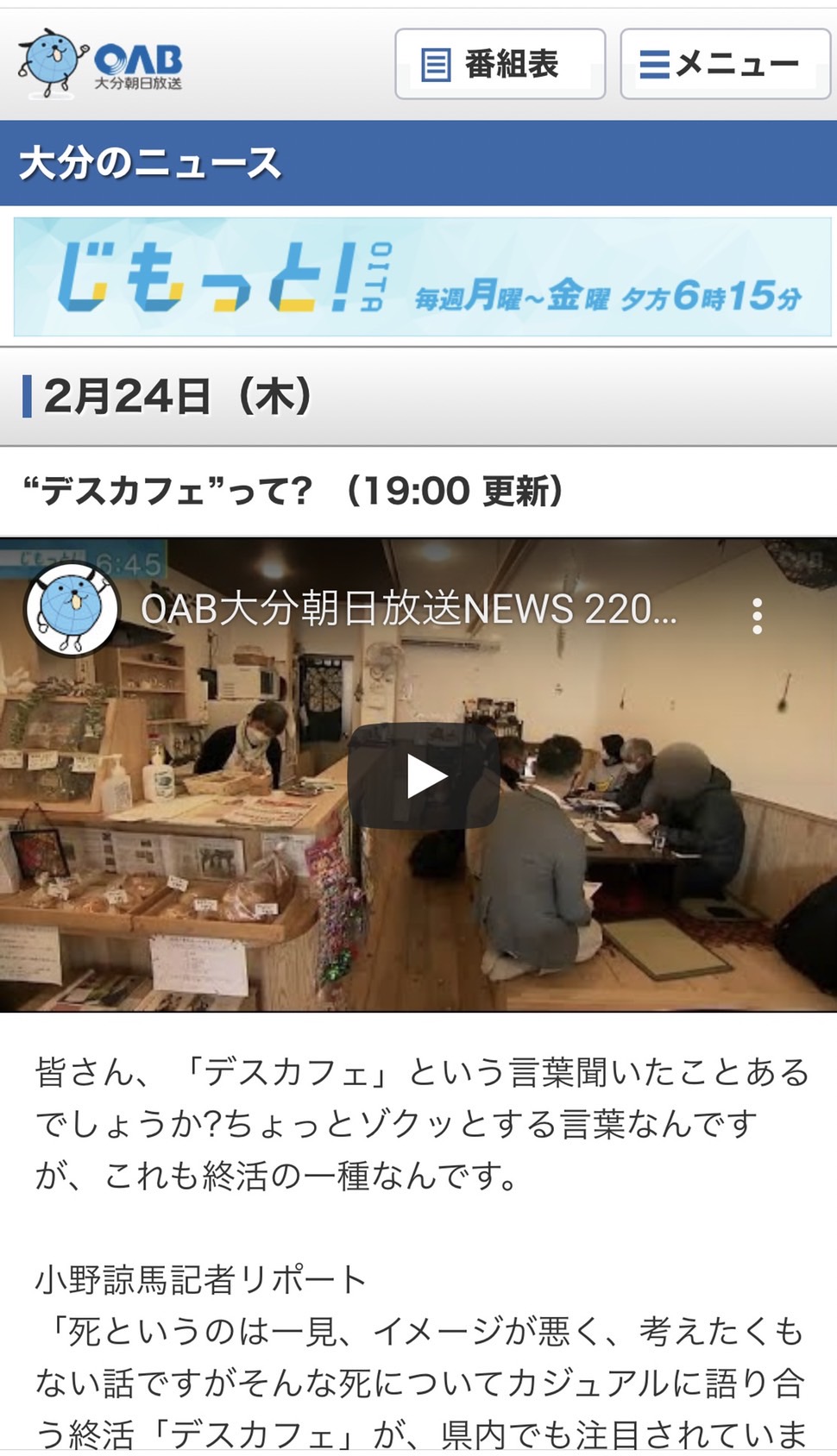新型コロナウイルスの感染防止のために、患者とその家族らの面会制限や禁止が続く中、身内の死に立ち会えなかったり、葬式ができずに会えた時は骨壺の中という社会現象が起きています。死について考える機会が増えた今、死をカジュアルに語り合う「デスカフェ」というコミュニティが注目されています。
デスカフェとは、1999年、スイスの社会学者が妻の死をきっかけに「死について気軽に
話し合う場」を作りました。その後、世界70か国で開催されるようにり、日本でも都心
部を中心に数年前から注目され、各地で開催されています。
実は、大分県での初開催は2022年1月に行われ、反響があったため今では、毎月開催されています。その場は、大分市敷戸団地の中にあるコミュニティカフェ 大きな樹。
地方都市の多くが抱える問題「団地の高齢化」。高齢化団地は様々な問題を抱えています。これらの問題を放置すれば、居住者の減少により住環境が悪化し、団地の外からの転入者が見込めなくなります。そうなるとさらに住環境が悪化していきます。そんな問題に取り組み、団地内と団地外の人が交流できるコミュニティカフェの役割です。
そんなコミュニティに、デスカフェというコミュニティが作られています。
死は誰にでも訪れます。しかも、それはいつなのかわかりません。そして人生は1度しか
ない。だれもが大切なことだとわかっていても、なんとなく「縁起でもないから」と避け
ている「死」。少子高齢化、単身世帯の増加という社会変化の中、大分市のデスカフェはあ
えて高齢化団地の中にあるコミュニティカフェ「大きな樹」で開催しています。
この取り組みが大分朝日放送(OAB ジモット!OITA!)で取材されました。
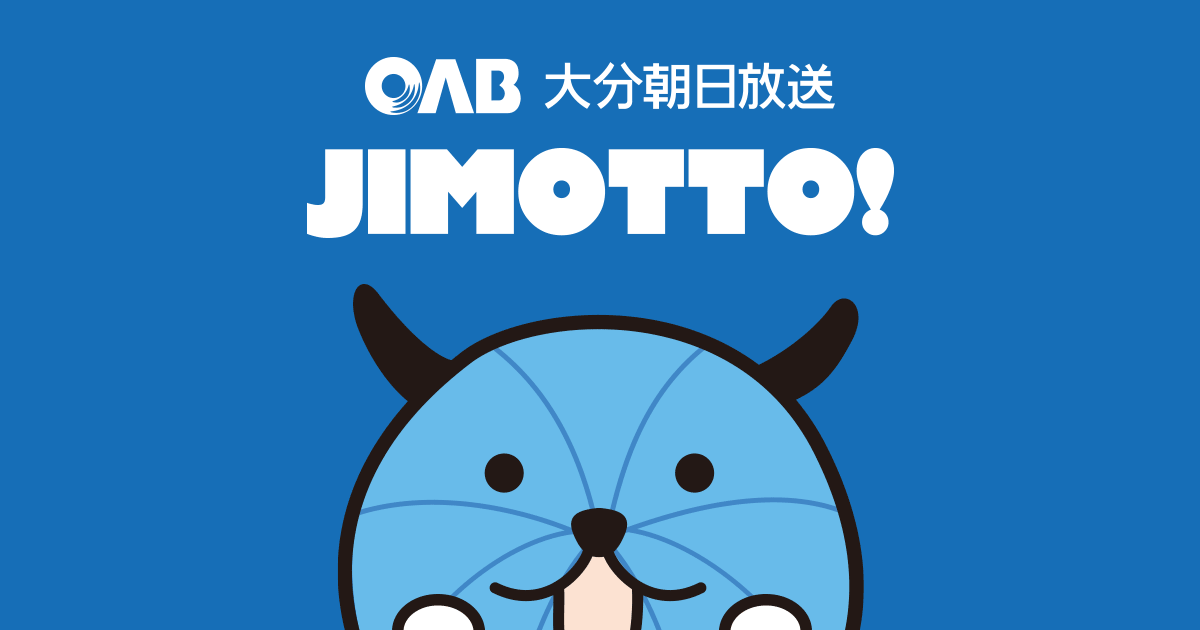
↓以下転載。
皆さん、「デスカフェ」という言葉聞いたことあるでしょうか?ちょっとゾクッとする言葉なんですが、これも終活の一種なんです。
小野諒馬記者リポート
「死というのは一見、イメージが悪く、考えたくもない話ですがそんな死についてカジュアルに語り合う終活「デスカフェ」が、県内でも注目されています」
今回、開かれたのは大分市の敷戸団地。高齢者や行政書士など、30代~70代の8人が参加しました。
デスカフェは1999年にスイスで生まれたとされこれまでに世界70カ国で行われています。
カードゲームなどを通して「死」について考え、将来、死を迎えるにあたり自分がすべきことのヒントを得ます。
一般社団法人まるっと終活大分支援協会 木原寛代表理事インタビュー
「終活といえば相続とか遺言っていうイメージがどうしても先行しちゃうんですけど、自分の人生について考えてほしい。それを考える人っていうのはなかなかいないんですよね」
参加者インタビュー
「私が司法・行政書士で就活とか遺言とかのお手伝いとか講義とかでお話をすることが多いんですけど、どうしても遺言を書くってなるとハードルとして高い。続く死が身近じゃないのかなとすごく感じている」
今回のデスカフェは、「余命半年で大切にしたいこと」をテーマに、自分が死ぬ時にどうありたいかを考え、今後の人生を明るくするのがねらいです。
「もしバナゲーム」というカードゲームで、余命半年を告げられたと想定し、死ぬまでに大切にしたい5つのことを選んでいきます。
参加者インタビュー
「結構難しい…」
「こっちの方が自分の感覚に近いかな…」
ゲームが終わると、それぞれが考えをまとめ、自分の死について意見を言い合います。
参加者インタビュー
「私自身もあと半年で死ぬって言われて不安にもなるんですけど、でもその後、私の妻だったり子どもたちって言うのは私がいなくなってその先生きていく中で私より不安なんだろうな」
一般社団法人まるっと終活大分支援協会 木原寛代表理事インタビュー
「ここは敷戸の高齢化した団地なんですけど、そんな各団地でデスカフェが自主的に開催されるようになって、県内各地でデスカフェが定期開催できるようになって、その地域の人たちがそれぞれ死について考えるコミュニティになっていければ」
運営するまるっと終活大分支援協会は、今後、月に一回のペースで定期的に開催する方針で、HPや電話で予約を受け付けます。