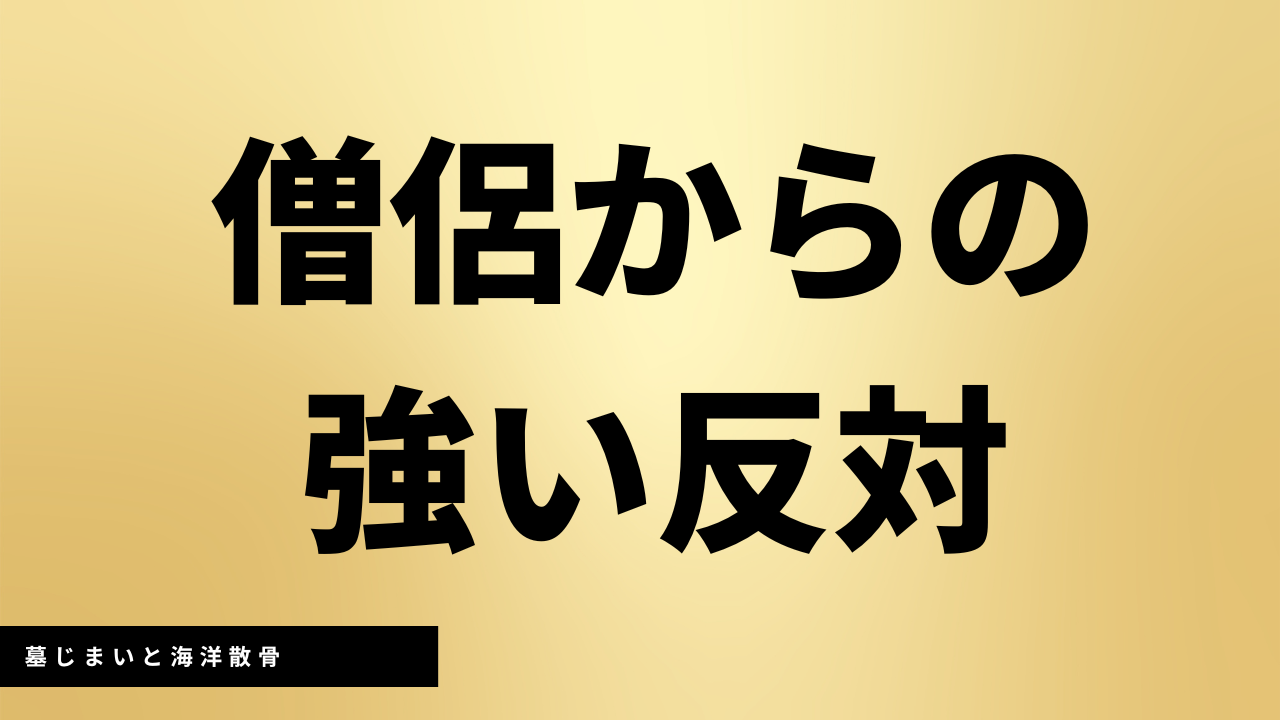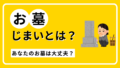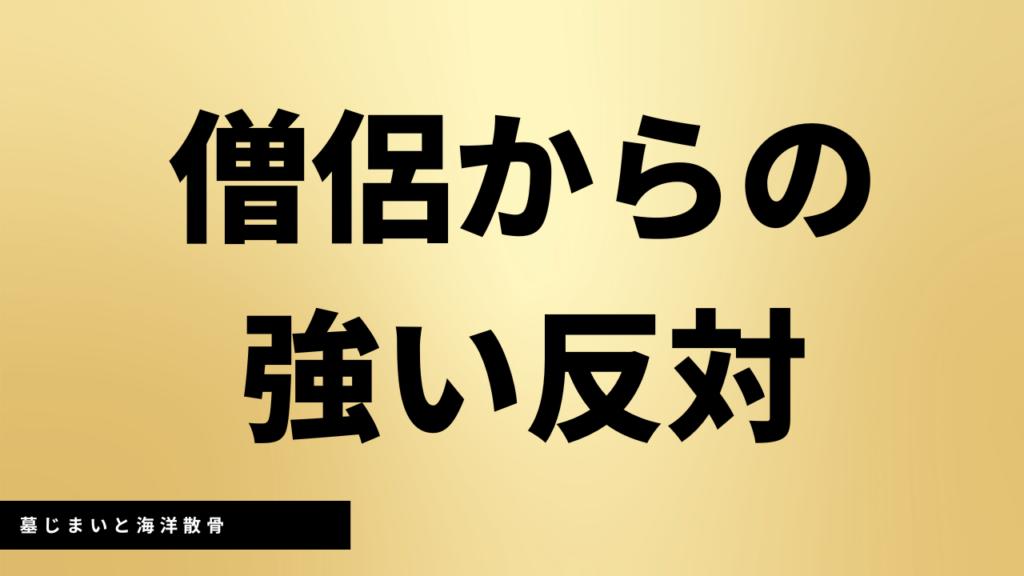
「散骨は供養にならない」
「遺骨を残さないと必ず後悔する」
大分県で墓じまいや仏壇処分を検討するご家庭から、こうした僧侶の言葉を聞いたという声は少なくありません。長年続いてきたお寺や宗派を守る立場からすれば、批判したくなるのかもしれません。しかし、その言葉をどう受け止めるかは、人それぞれです。
今回は、ある家族が僧侶との対話を通じて「供養の本質」を見つめ直し、最終的に海洋散骨を選んだ事例をご紹介します。
僧侶からの強い反対
夫を亡くした妻は、墓じまいと仏壇処分を検討していました。子どもたちは県外に住んでおり、大分に戻る予定はありません。お墓を守る人も、仏壇を引き継ぐ人もいない状況でした。
そんな中で選んだのが「海洋散骨」。夫は生前から「お墓はいらない、自然に還してほしい」と話していたからです。
しかし、菩提寺に相談したところ、住職からは強い反対の言葉が返ってきました。
「散骨は供養にはならない」
「遺骨を残さなければ必ず後悔する」
妻は迷いました。本当に夫を海に還しても良いのだろうか、と。
対話の中で漏れた言葉
しかしその対話の中で、住職の口からこんな言葉も漏れました。
「供養の本質は“形”ではなく“心”だ」
その一言に、妻は深くうなずきました。仏壇がなくても、お墓がなくても、夫を想う気持ちは変わらない。子どもたちがどこに住んでいても、海を見れば父を思い出せる。
この気づきが、妻にとって大きな後押しとなりました。
海洋散骨という新しい選択
最終的に家族は、墓じまいと仏壇処分を済ませ、夫を大分の海へと送りました。海洋散骨の当日、家族は花を手向け、「ありがとう」と声をかけました。
波に揺れる花を見ながら、妻は心の中で「これで良かった」と思えたそうです。お墓や仏壇という「形」がなくても、夫はいつでも心の中に生き続けています。
変わる社会、変わる供養のかたち
大分でも、「墓じまい」「仏壇処分」「海洋散骨」を選ぶ人は確実に増えています。理由は明確です。
- 跡継ぎがいない
- 子どもに負担をかけたくない
- 自然に還りたいという本人の希望
昭和30年代に火葬と墓地埋葬法が一般化するまで、日本では土葬が主流でした。遺骨を残して守る文化は比較的新しいものです。それ以前は「自然葬」が当たり前であり、供養は仏壇や位牌などの「形代(かたしろ)」を通じて行われていました。
つまり、海洋散骨は決して「文化を壊す」ものではなく、むしろ古来の自然に還る供養に立ち戻った選択肢なのです。
僧侶との対話が教えてくれたもの
今回の家族は、僧侶からの反対を受けながらも、その対話の中で「供養の本質は心」という言葉に気づきを得ました。
墓じまいも仏壇処分も、海洋散骨も、最も大切なのは「心からの感謝」と「家族が納得できる形」です。形式ではなく、故人への思いそのものが供養なのです。
大分で墓じまいや仏壇処分を考えている方へ。どうか、他人の声に惑わされるのではなく、家族の気持ちと故人の意思を大切にしてください。
海はどこまでも広く、あなたの祈りを受け止めてくれる場所です。