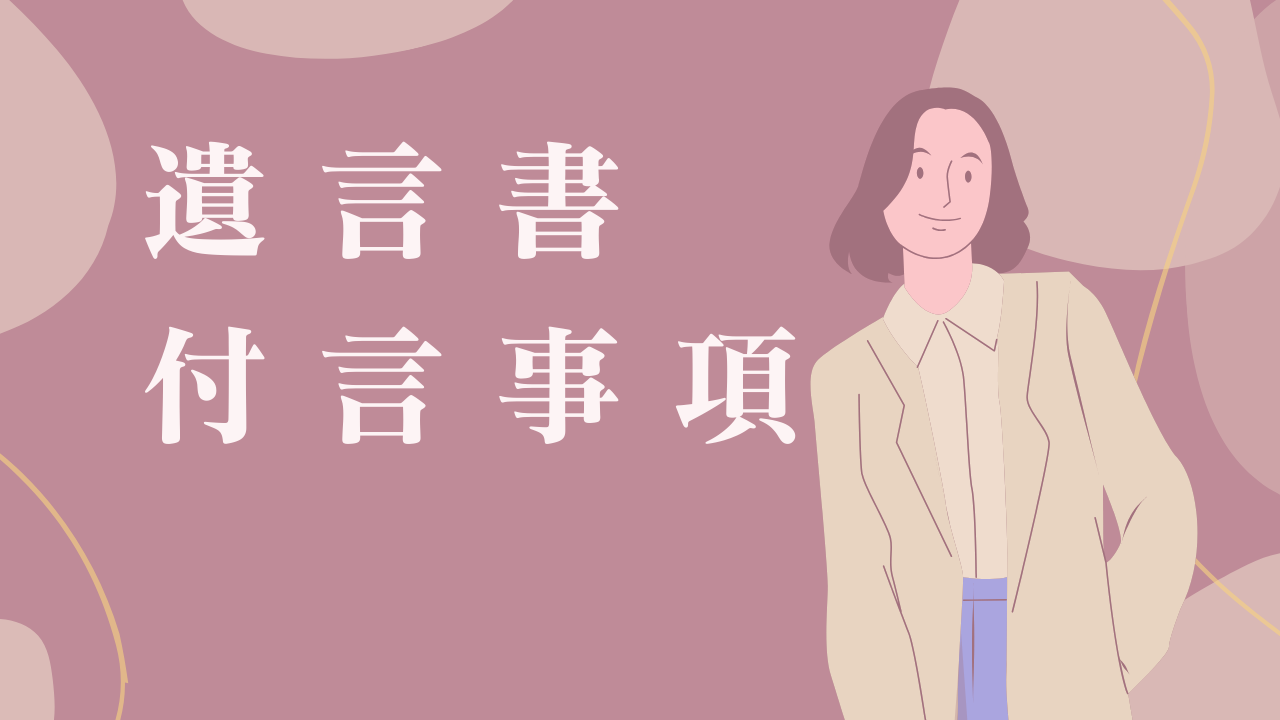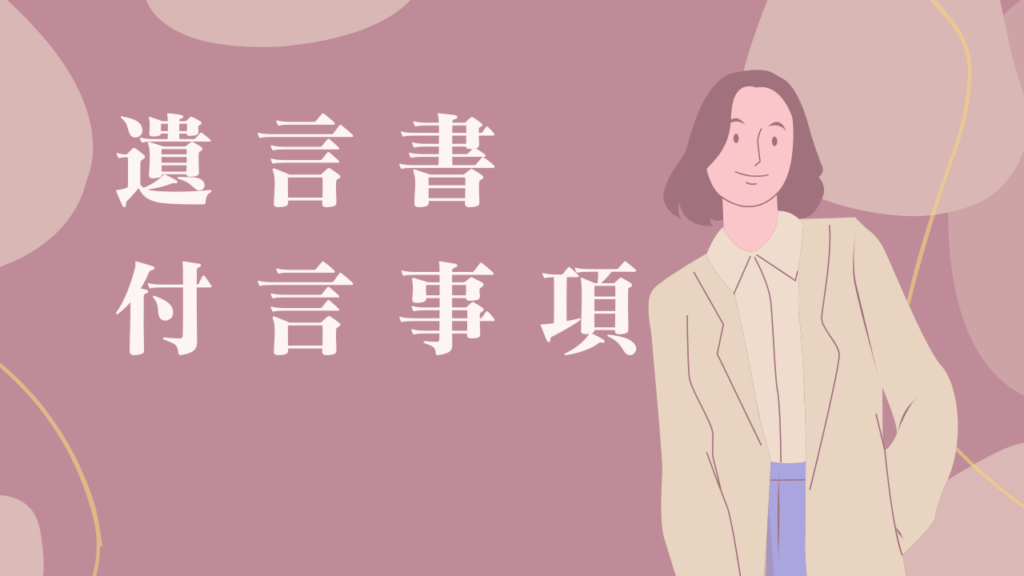
大分県でも、家族間の不仲やわだかまりが、そのまま相続トラブルに発展するケースは少なくありません。トラブルを防ぐためには、遺言書の作成や家族間の話し合いを早めに行うこと。また、遺言書の内容がトラブルのタネにならないか、専門家のチェックをうけるのも大切です。入念な準備が、残された人の心の平穏につながります。
今回は、義姉との不仲がトラブルに発展してしまったという、大分市に暮らす50代の女性のエピソードをご紹介します。
義母の相続で、義姉の不満が爆発
私は大分県で暮らす50代の主婦です。少し前に夫の母(義母)が亡くなったとき、家族の間で大きな相続トラブルが起きてしまいました。今振り返ると、私と義姉の不仲が、そのまま相続の問題を複雑にしてしまったのだと思います。
仲が良かった義母との関係が、トラブルの火種に
夫の姉は、結婚当初から私に対して厳しく、何かと意見が合いませんでした。義母も「娘があなたにきつく当たってごめんね」と口にしていたほどです。義姉とは不仲でしたが、私は長男の嫁ということもあり、義母とは同居しながら仲良く暮らしていました。私が義母の介護をしたこともあり、義母が残した遺言書には「自宅の土地建物は長男(私の夫)に相続させる」とだけ書かれており、私たち夫婦以外の親族には一切触れていませんでした。
そのため、葬儀後の相続手続きで義姉から強い不満が出ました。
「母はあなたたちだけに良い思いをさせるつもりだったのか」
「あなたが遺言書の内容にも口を出したんじゃないか」
と、感情的な言葉が飛び交い、話し合いは平行線。もともとの不仲が尾を引き、義姉との関係は一時断絶寸前になってしまいました。
最終的には弁護士を通じて調停となり、相続分の一部を金銭で支払う形で和解しましたが、家族の関係は大きく傷つきました。
遺言書が感情のもつれを生まないよう、内容にも配慮を
この経験から学んだのは、「相続は感情と直結する」ということです。遺言書を作っていても、一方的な内容だと逆に火種になる場合があります。
行政書士に相談した際に教えていただいたのが、遺言書に「付言事項」を添える方法でした。
「娘と嫁との関係で誤解があるかもしれないが、私自身は子どもたち全員を大切に思っている」
「自宅は長男に残すが、その代わりに預貯金を他の子に遺したい」
といった一言を添えておけば、相続人の納得度は大きく違っていたかもしれません。
また、遺言書の内容を事前に家族で共有する「家族会議」も有効だと思います。遺言書の内容を、亡くなってから知るのではなく、生前にある程度理解しておけば、トラブルを避けやすくなると思います。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
相続トラブルは、「自分の家族には関係ない」と思っている方こそ注意が必要です。相続は誰にでも訪れる問題。だからこそ、日頃から準備しておくことが大切なのです。
終活についてお悩みがあれば、当協会にお気軽にお問合せください。ご本人やご家族の気持ちに寄り添った終活の形をご提案します。