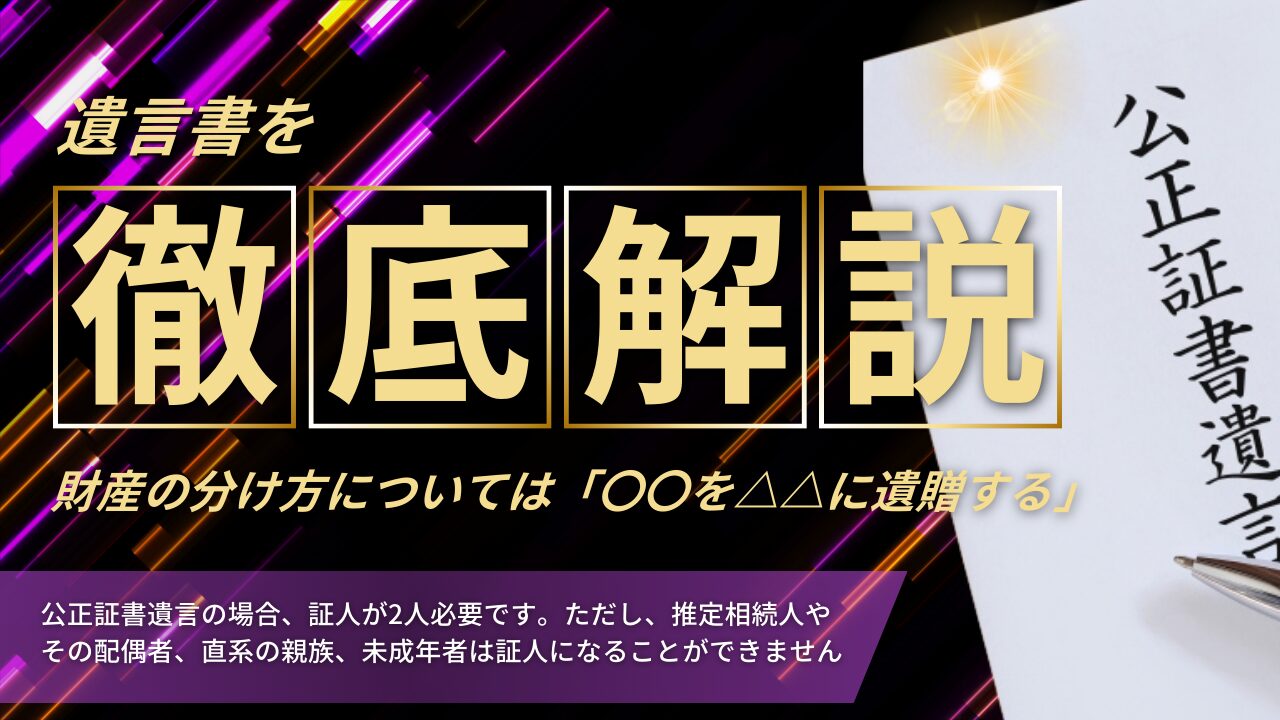まるっと終活大分支援協会には、終活にまつわる様々なご相談やお問い合わせをいただきます。近ごろは、年齢に関わらず遺言書の作成を考える方も増えています。遺言書は、あなたが亡くなった後、財産をどう分けるか、またはどのように処理すべきかを明確にするための重要な書類です。しかし、その作成には注意すべきポイントがいくつかあります。この記事では、遺言書を作成する際に注意すべき点を紹介します。遺言書の作成は、元気なうちに考えて、行動に移しておくことが重要です。ぜひ参考にしてみてください。
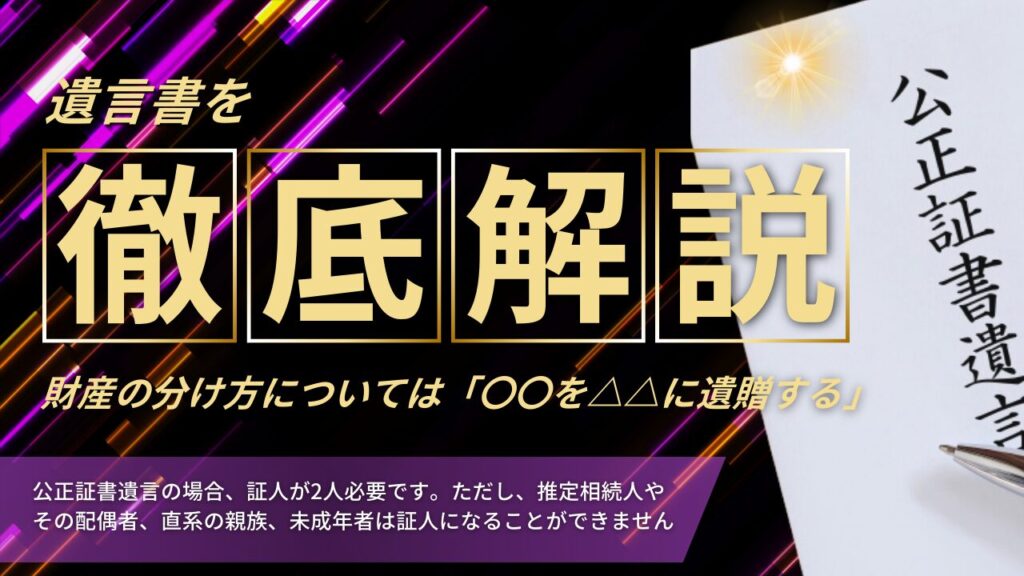
手軽に作成できる「自筆証書遺言」と、法的効力が確実な「公正証書遺言」
遺言書にはいくつかの形式がありますが、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が主流になっています。それぞれの特徴を理解して、ご自身に最適な形式を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言
自分で書く遺言で、比較的簡単に作成できます。ただ、すべて自筆で記す必要があるなど、法的な要件を満たしていないと無効になってしまうことがあります。
公正証書遺言
公証人が作成を手伝う遺言です。確実に法的効力を持ち、後で紛失する心配もないのが利点ですが、公証人との打ち合わせが必要だったり、公証役場に出向くなど、時間と手間がかかります。
後々の紛争を避けるためにも、内容は明確に記載しましょう
遺言書に記載する内容は、非常に重要です。相続人が誤解しないよう、具体的に記載することが大切です。例えば、財産の分け方については「〇〇を△△に遺贈する」といった具体的な表現を使うこと。曖昧な表現だと、相続時にトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
証人を立てる場合は、信頼できる人に依頼を!
公正証書遺言の場合、証人が2人必要です。ただし、推定相続人やその配偶者、直系の親族、未成年者は証人になることができません。ご自身で証人を手配する場合は、信頼できる人を選ぶことが大切です。
遺言書の保管場所にも注意が必要
遺言書は保管方法や保管場所にも工夫が必要です。自筆証書遺言の場合は、自宅に保管していると紛失したり発見されない場合があります。信頼できる人に、遺言書の存在や保管場所を伝えておきましょう。遺言書を法務局に保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、紛失等のリスクがなくなり、家庭裁判所の検認手続きを省略することができます。
遺言書の内容は、定期的に更新しましょう
遺言書は一度作成したら終わりではありません。財産状況が変わったり、相続人に変動があったりした場合は、遺言書を更新する必要があります。その際は、新しい遺言書が作成されたことを明示的に示しておくことも大切です。
疑問点や不安なことは専門家に相談を
遺言書の作成は、法的な知識を要することがあります。ご自身で作成することもできますが、疑問や不安なことがあれば、専門家に相談することが大切です。特に複雑な財産や相続が絡む場合には、専門家の助けを借りることをおすすめします。
終活や相続、墓じまい、海洋散骨のご依頼は当協会まで
今回は、遺言書の書き方について解説しました。
ただ、遺言書の作成に限らず、現実問題として終活に取り組んでいる方は、実は稀です。多くの方は、「まだ先で大丈夫」と考えているようです。ただ、「いつかやればいい」と先延ばしにすると、あなたの意思が実現できなかったり、思わぬトラブルに発展することもあるのです。人生100年時代、元気なうちにご自身の老後や死後のことについても考えておくことが大切です。そして、終活で重要なのが、お墓と供養の問題です。近ごろは、墓じまいに着手する方も増えています。また、自然や環境、遺族にも優しい海洋散骨を検討する方も増えています。
墓じまいや海洋散骨についての相談は当協会にお気軽にお問合せください。